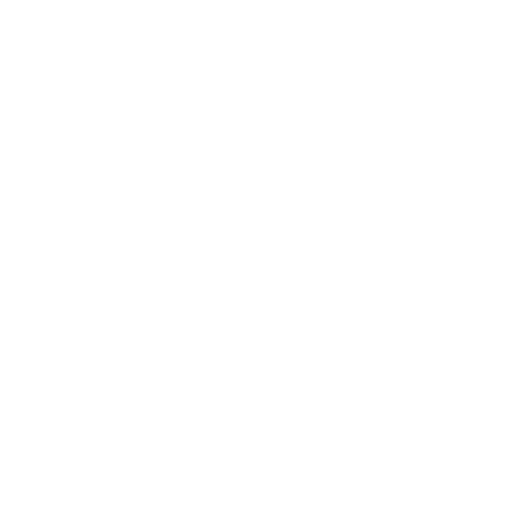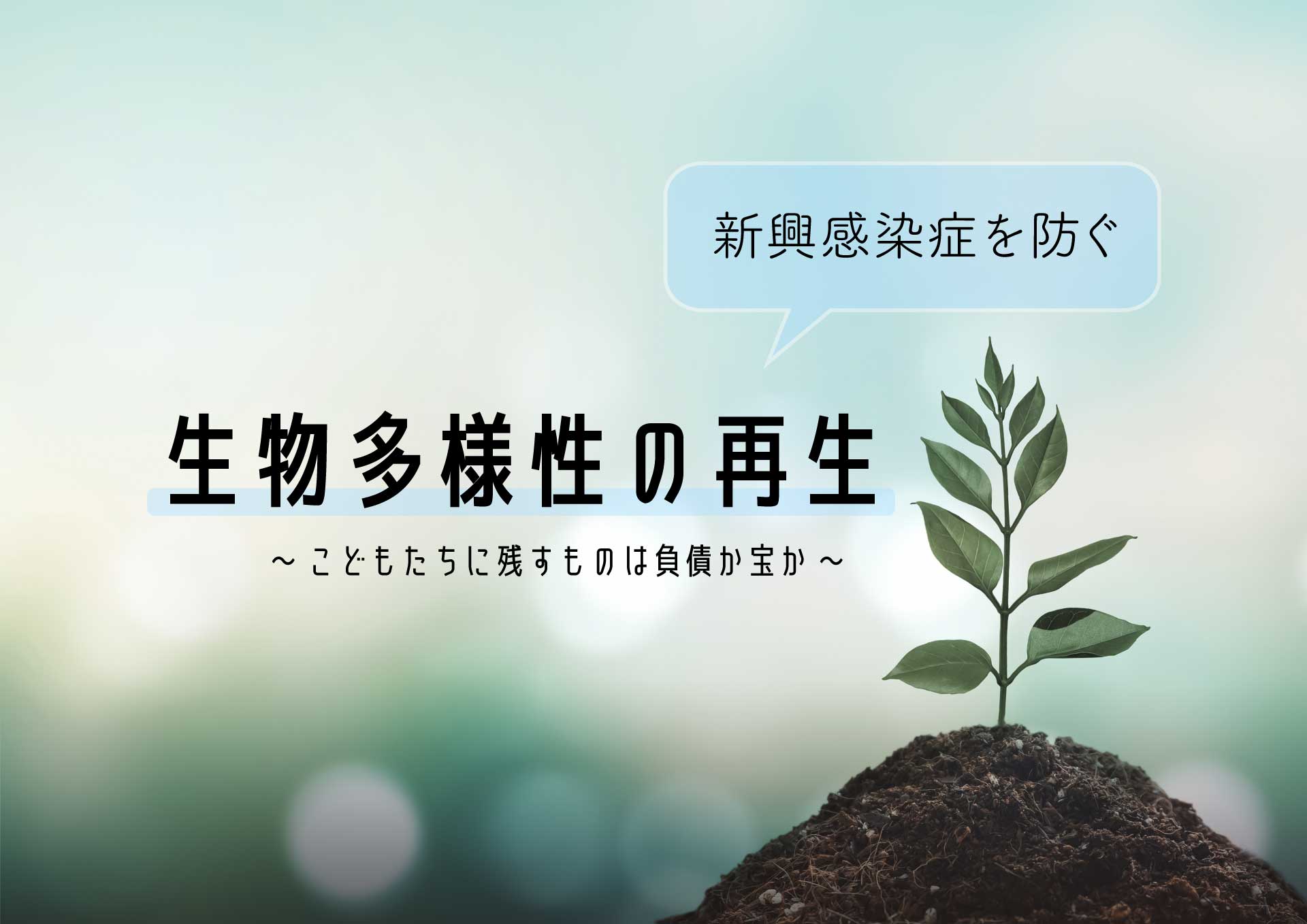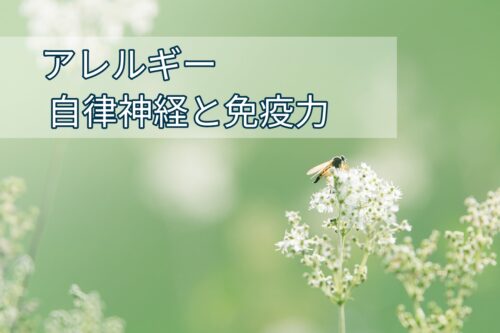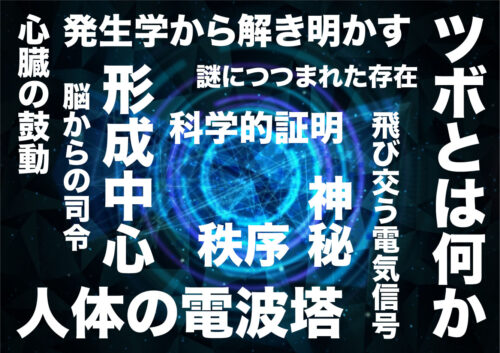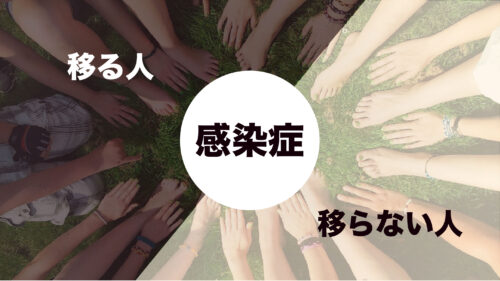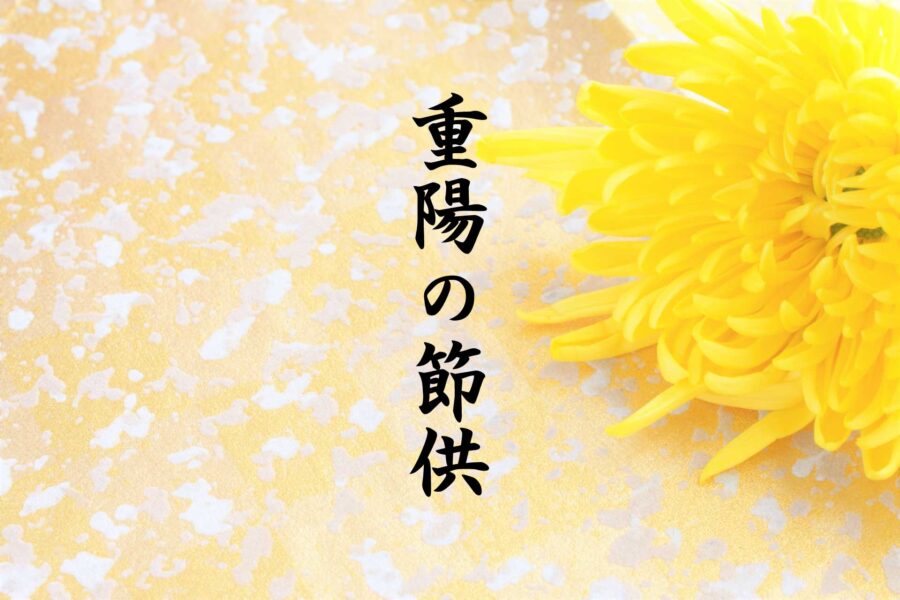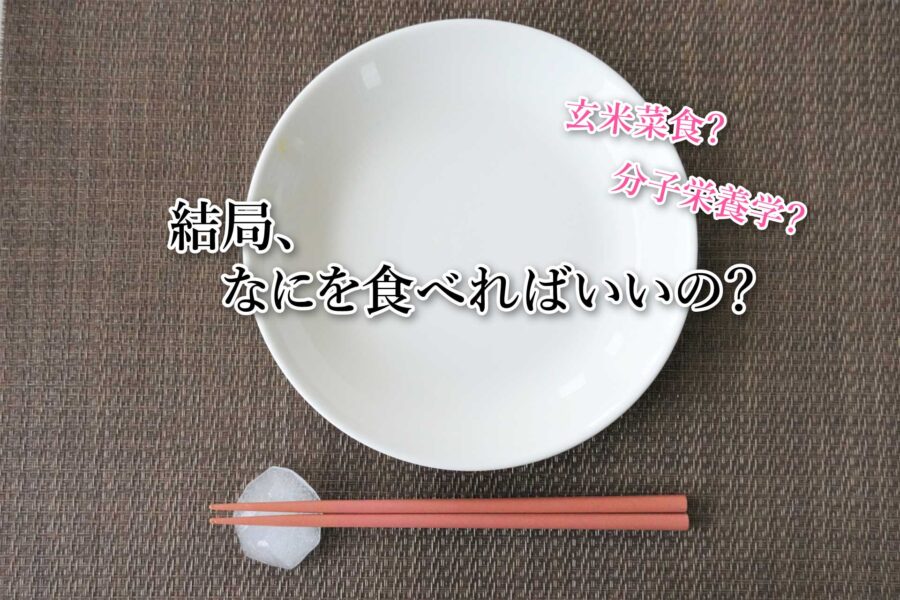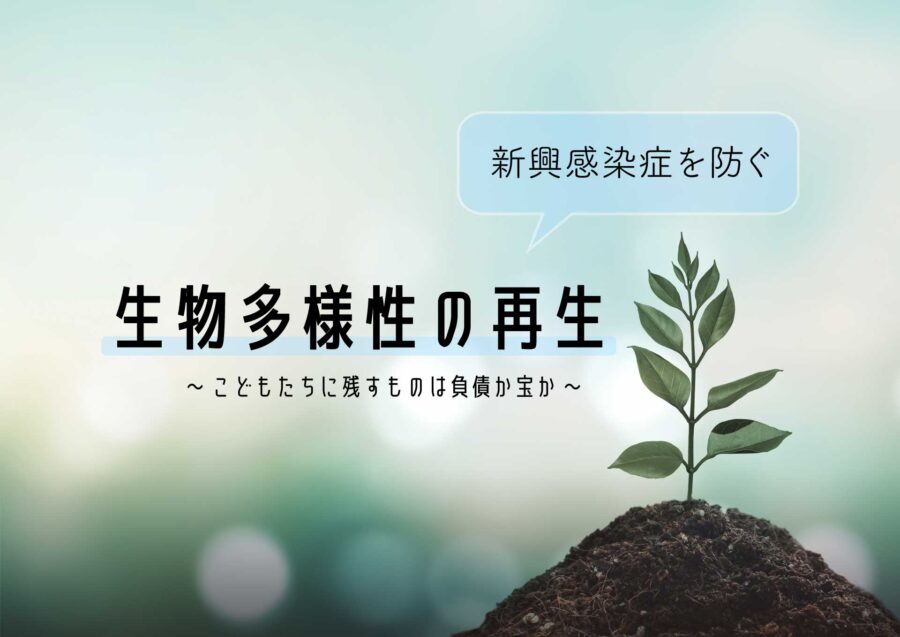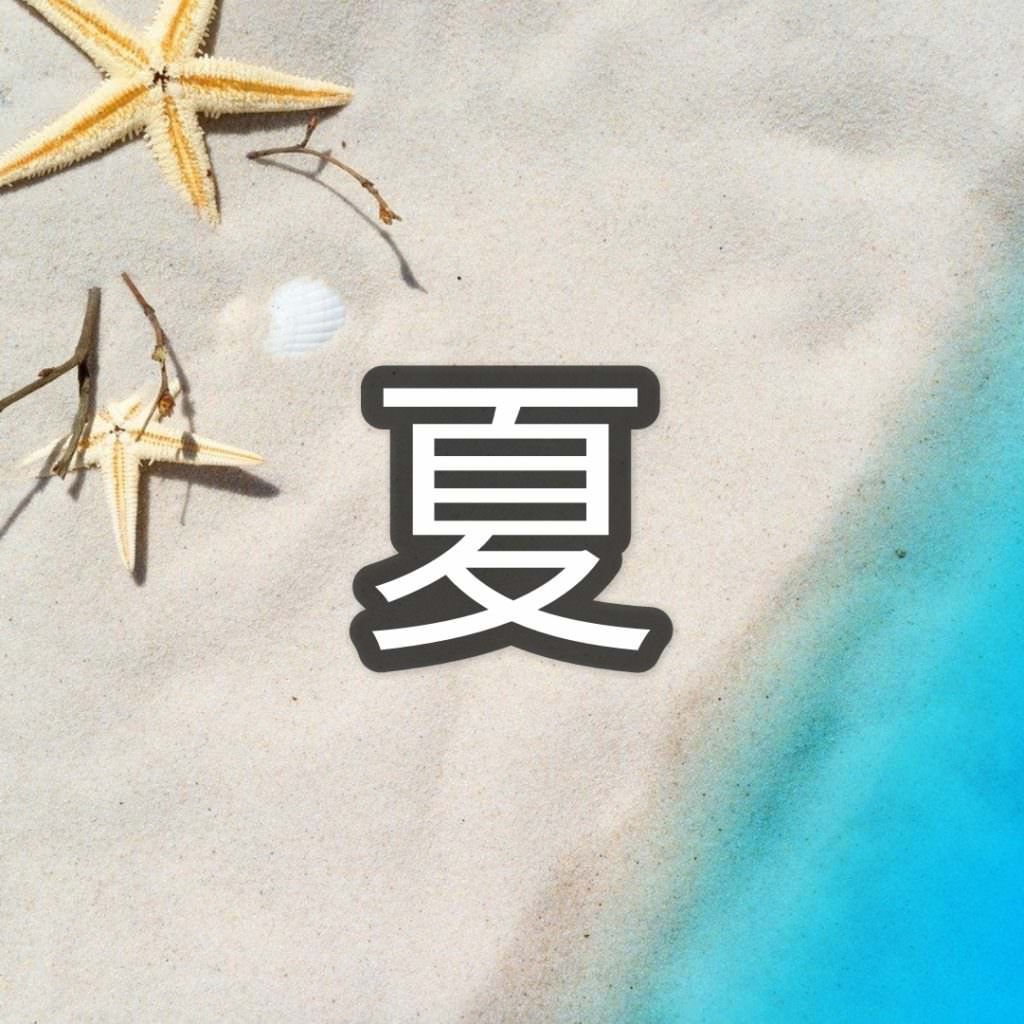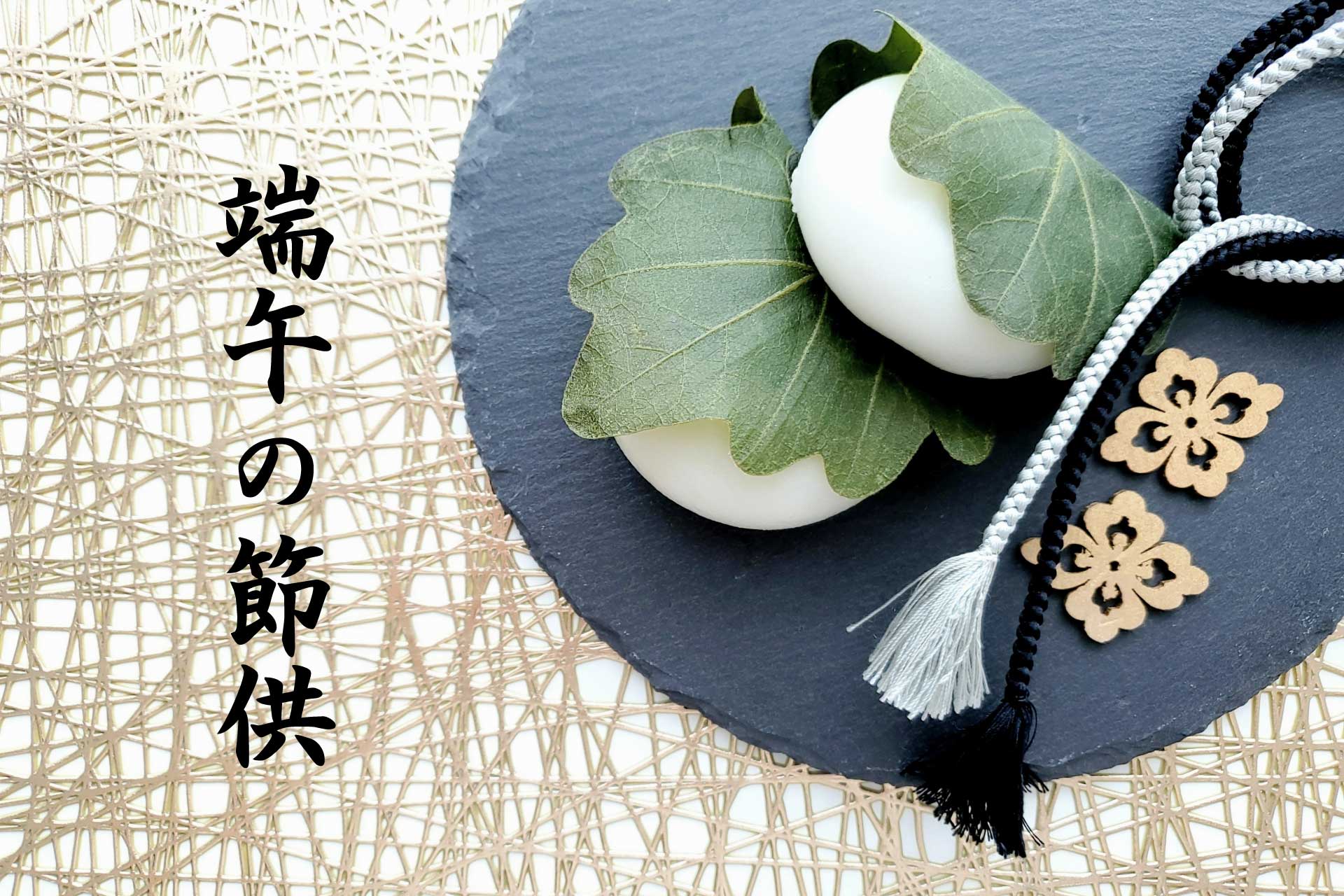
◇ 読み方「たんごのせっく」
こどもの日として親しまれています。
本来は旧暦の5月5日。
今は新暦の5月5日なので、昔と比べると一か月ほど早くなります。
節供と節句
「せっく」を節句と書かれることも多いですが、元は「節供」
文字からわかるように、お供えの意味を含みます。
武士を尊ぶ「しょうぶ」

菖蒲(しょうぶ)は薬草として知られ、魔除けとしても使われてきました。
「尚武(武士を尊ぶ)」「勝負」と音が同じで武士はこの節供を重んじたとのこと。
元々は女子の節供でしたが、武士社会になって男子のたくましい成長を願うものへと変化したそうです。
鯉のぼりも、武家の幟(のぼり)が起源とされています。
端午の節供では、菖蒲酒を飲んだり 菖蒲湯につかることで邪気を祓います。
家系が途絶えない「柏餅」

柏の葉は、次の葉が出てくるまで落ちないことから、家系が継承されていくという縁起物。
子孫繁栄の願いが込められているんですね。
一年に一度、このような背景に思いをはせてみてはいかがでしょうか?