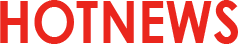真の愛国心 - 矢内原忠雄 訳
国を偉大にする一の方法
長く外国におり、しかも日本人と交わること少く、かえって日々多数の国の人々と交わっていると、各国の国民性をいくらか窺うことが出来るように思う。我輩の勤めている役所に来ている人々は 公式にその国の政府から任命されたるものでないから、国家または政府を代表するものではないが、国民そのものはこれを代表せざるを得ない。政府はこれを任命しないとしても、これを推薦するのであるから自分の国民を辱めるような人を出すはずはない。従ってこの役所に集まって来る人々は、国民性の長所を備えているものであるというも過言であるまい。故に日々交わっていて不愉快と思うものは甚だ少く、性質の善く、交り易い人が多く、仕事するにも自ら愉快である。他山の石以て玉を磨くべしという教が世に伝えられているが、僕は各国人と交わり、各国人の長所を学びたい心持する。例えば某国人は頗る勤勉である。ある国人は快闊である、ある国人は機敏である、ある国人は耐忍が強いというが如く、他国人の長所を見るにつけても、自分の短所が一層明になると思う。かくいうたならば、あるいは謙遜に過ぎて卑屈になる恐もありとするものもあるであろうが、仮りに僕自身は個人としてこの過があるとしても、国民全体はなかなか謙遜の態度を執る恐もないから、僕は寧ろ我国民性に如何なる欠点あるかを省るのが国を偉大にする一の方法でないかと思う。言葉を換えて言えば反省、自己の過を知ること、己の短所を自覚すること、これが大に伸びんとする前に大に屈せねばならぬという訓に適うことで、これがなければ国民は慢心するのみである。慢心は亡国の最大原因である。
米国詩人の無遠慮な詩
我輩の友人にアーヴィンという文士として相当に名を轟かした米人がある。この人が昨年の夏頃作った詩がある。これを読んで我輩は大に感服した。事は日本に関することであるから、必らずや我国語に翻訳せられ、または有識者の間には原詩が大に広まれるものと思い、これを友人間に質したが、更に伝わっていないと聞いて大に残念に思うた。
詩の題は「隣邦の日本よ、しばし待て」(Wait neighbour Japan)というのである。しかしてその要点は世界の歴史を繙けば、国が亡びんとする前には、国が富みその兵が強くなる。国民が慢心して終には亡ぶるものである。米国は今まさにその轍を踏まんとしている。隣邦の人よ、しばし待て、汝に無礼するものは自ら亡ぶというので、このことを無遠慮に詠じている。我輩はこれを読んで非常に驚いた。彼がその同胞なる米国人を警戒するに親切であることは、彼の従来の著書に現われているが、かくも露骨に、しかも外国人にあてて自国人の欠点を忌憚なく述べた彼の勇気は実に敬服の至りである。またも一歩深く立ち入って彼の心情を窺えば、彼の真意はその同胞を警戒するにありとはいえ、言葉として外に現われたものは、殆ど同胞を侮辱するが如き烈しい用語を以てする必要を彼が感じた心持に強く同情せざるを得ない。同時にまたかくの如き言をなせる彼のこの詩を読む米人の心持にも感激せざるを得ないのである。もし地を替えて、同じ詩を日本人が書き、これを日本の新聞か雑誌かに掲げたなら、如何なる非難を受けるかと思えば、僕はかえって隣邦米人の心持の広きを羨しく思うのである。
予言者あって国は偉大となる
僕はこの詩を読んで、その作者の奇抜にして国を愛するとともに人道を重んずるに感じ、同時にかくの如き人が何れの国を問わず国民の中にあったならば、それこそいわゆる国の師ともいうべきものであって、旧約全書に現われた猶太の予言者というものも即ちこういう人であったろうと推量する。彼はその国を愛するためにその国の短所を指摘して、彼らの執るべき道を教えかつ彼らを導いてくれたのである。ただ惜むらくは予言者は自国に名誉を得ない、とかく彼らはいわゆる愛国者のために排斥せられ迫害され、その予言の的中するまでは無視され勝なものである。けれどもこういう人があって始めて国家は偉くなるものと思う。自分の一身を顧みず、道のために動く人がなければ、国は愛国者と称するデマゴーグの口に乗せられて、国運の傾くのを寧ろ助けるような始末になる虞がある。
この種の人は必らずどの国にもあるものと思う。現に僕は伊国に於ても仏国にでもかくの如き人あることを知っている。また独逸にも同様の人が今は追放同様の身になっているのを知っている。露国の如きに至ってはこういう人が数多あって、何れも外国に流浪し、寒天に着るものもなく窮居している。
真の愛国者の態度
せんだって某国人と談話を交えている間に、その人曰く、我国が貴国に言語道断の態度を執ったのは、決して国民の大多数の意志を表わしたものでない、少数の政治家が選挙運動の都合からかの挙に出たものである。しかしいやしくも国家の大責任を有するものがああした態度に出たことは、そもそも我国の大に恥とするところである。自分は自分の国ながらも愛想がつきて、その国内に住むを屑しとせぬというた。これは一応我輩に対する言訳のお世辞であるとのみ思うていたが、この人はその後、自国の家を引払って仏国の南部に家を構えた。爾後二ヶ月たったかたたぬ間に同様の話を他の人から聞いた。その人は当時外国にいたのであるが、そのまま其所に住んで本国に帰らぬというていた。
あるいはこの人々の行為を以て非愛国の人と称する人もあるか知らぬ。しかし自分の政府の為したことは、何事にもあれこれであるが如く認め、これに賛同しこれを助けることが果して真の愛国心であろうか。理非曲直の標準は一国に止まるものでなく、人類一般に共通するものである以上、寧ろ是は是、非は非と明に判断し、国が南であれ北であれ、はたまた東であれ西であれ、正義人道に適うことを重んずるのが真の愛国心であって、他国の領土を掠め取り、他人を讒謗して自分のみが優等なるものとするは憂国でもなければ愛国でもないと僕は信じている。
西洋にも現在伯夷叔斉あり
僕は右に挙げた二の例に接した時、直に心に浮んだことは伯夷叔斉の話である(※ 伯夷叔斉の話)。この兄弟は国を愛すること熱烈で、周の武王が木像を載せて文王と称し、主君の紂を討つ時、彼らは父が死んで葬らぬ間に干戈を起すは孝行でなく、臣が君を弑するは仁でないといって武王を諫めたが用いられなかった。その国を愛するの情は武王自身または太公望呂尚にも譲らなかったろう。彼の眼には憂国より一層高いものがあって、その高いものに法って始めて愛国が意義をなすのである。不正の方法を以て勢力を得るはかえって己の国を弱くするものであるとなし、義、周の粟を食わずといって首陽山に隠れた。あるいは彼らの見識が過っていたこともあろう、現に周の時代は八百余年の久しい間続き、その政治は今日も模範として賞められているに見ると、両人の識見にも遺憾の点があるかの如く思わるるも彼らの隠れた動機に至りてはなお今日大に学ぶべきことであって、孔子が伯夷叔斉の如き善人と謂うべきものと称賛したのも無理ならぬことである。前に述べた二人の某国人の心持の如きは、取りも直さず伯夷叔斉の心持を以て、自国の粟を食わずといって他国にその居を転じたので、そのやり方は同じである。伯夷叔斉の時代に海外に渡る大船があったなら、恐らく首陽山に隠れないで、日本辺りに来たのであったろう。
愛国心の現わし方
我国には国を愛する人は多くあるが、国を憂うる人は甚だ少い。しかしてその国を愛するものも盲目的に愛するものがありはせぬかを虞る。かつてハイネの詩の中に、仏人が国家を愛するは妾を愛するが如く、独逸人は祖母を愛する如く、英国人は正妻を愛するが如くであるというた。妾に対する愛情は感情に奔ることが多く、可愛い時には無闇に愛するが、ちょっと気に入らぬ時にこれを擲打するに躊躇せぬ。祖母を愛するのは御無理御尤一天張りである。正妻を愛するのは、妻の人格を重んじ、自己の家と子供との利害を合理的に考え合せて愛するので、妻に過があればこれを責めて改悛させるその愛情は一時的の感情に止まらぬのである。世人はよく国際の関係には道徳なく、正義人道が行われないというものもあるが、我輩の見る所では、決してこれらのものが皆無であるということはない。今日はいまだ何事もこれらの標準によりて決せらるるとは言い難いのであるが、しかし早晩国の地位を判断するには正義人道を以てする時が来るのである。近頃は何れの国でもその心事を隠すことが出来ない、国民の考えていること、政府の為したことは、殆ど総て少時間の後に暴露し、列国環視の目的物となる。そこで世界の各国が一国を判断する時には、その言うこと為すことの是非曲直を以て判断する、あるいはその代表者が如何なる言を発したか、如何なる行動を執ったかによりて判断する、またある国が卑劣であり、姑息であり、陰険であり、または馬鹿げたことをすれば、それは直に世界に知れ渡るのである。従てある国が世界のため、人道のために如何なる貢献をなしたかは、その国を重くしその威厳を増す理由となる。国がその位地を高めるものは人類一般即ち世界文明のために何を貢献するかという所に帰着する傾向が著しくなりつつある。
一九二五年一月一五日
『実業之日本』二八巻二号
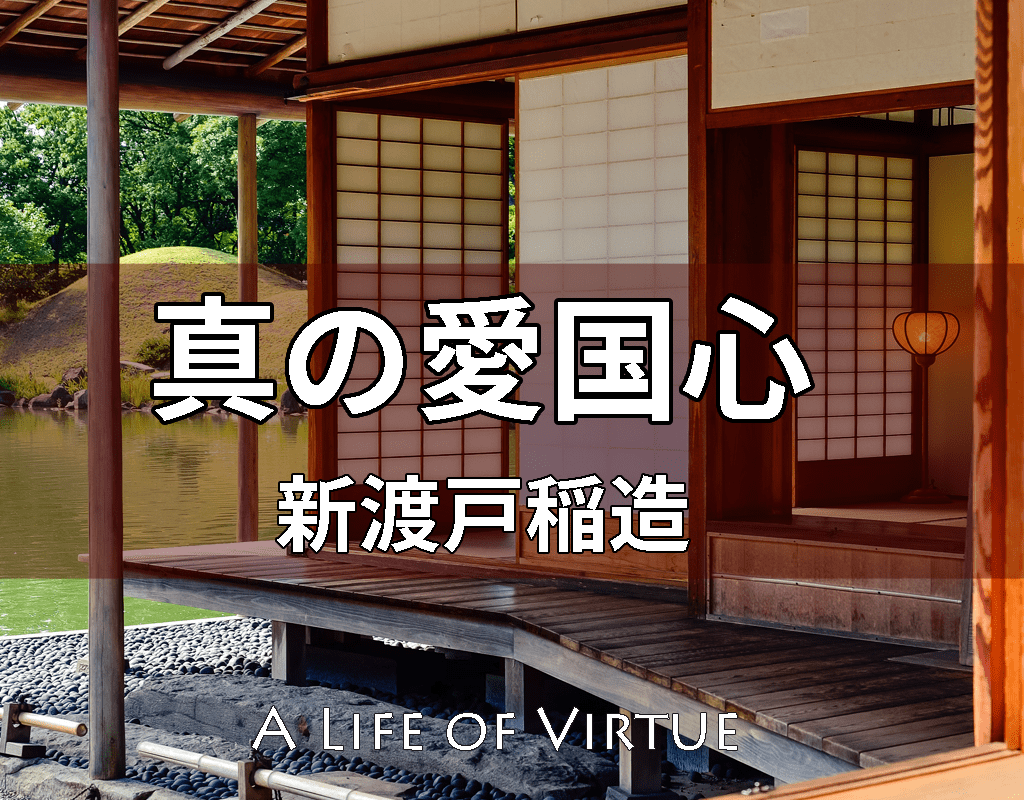 p.2
p.2