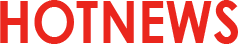第五章 芸術鑑賞
諸君は「琴ならし」という道教徒の物語を聞いたことがありますか。
大昔、竜門の峡谷に、これぞ真の森の王と思われる古桐があった。頭はもたげて星と語り、根は深く地中におろして、その青銅色のとぐろ巻きは、地下に眠る銀竜のそれとからまっていた。ところが、ある偉大な妖術者がこの木を切って不思議な琴をこしらえた。そしてその頑固な精を和らげるには、ただ楽聖の手にまつよりほかはなかった。長い間その楽器は皇帝に秘蔵せられていたが、その弦から妙なる音をひき出そうと名手がかわるがわる努力してもそのかいは全くなかった。彼らのあらん限りの努力に答えるものはただ軽侮の音、彼らのよろこんで歌おうとする歌とは不調和な琴の音ばかりであった。
ついに伯牙という琴の名手が現われた。御しがたい馬をしずめようとする人のごとく、彼はやさしく琴を撫し、静かに弦をたたいた。自然と四季を歌い、高山を歌い、流水を歌えば、その古桐の追憶はすべて呼び起こされた。再び和らかい春風はその枝の間に戯れた。峡谷をおどりながら下ってゆく若い奔流は、つぼみの花に向かって笑った。たちまち聞こえるのは夢のごとき、数知れぬ夏の虫の声、雨のばらばらと和らかに落ちる音、悲しげな郭公の声。聞け! 虎うそぶいて、谷これにこたえている。秋の曲を奏すれば、物さびしき夜に、剣のごとき鋭い月は、霜のおく草葉に輝いている。冬の曲となれば、雪空に白鳥の群れ渦巻き、霰はぱらぱらと、嬉々として枝を打つ。
次に伯牙は調べを変えて恋を歌った。森は深く思案にくれている熱烈な恋人のようにゆらいだ。空にはつんとした乙女のような冴えた美しい雲が飛んだ。しかし失望のような黒い長い影を地上にひいて過ぎて行った。さらに調べを変えて戦いを歌い、剣戟の響きや駒の蹄の音を歌った。すると、琴中に竜門の暴風雨起こり、竜は電光に乗じ、轟々たる雪崩は山々に鳴り渡った。帝王は狂喜して、伯牙に彼の成功の秘訣の存するところを尋ねた。彼は答えて言った、「陛下、他の人々は自己の事ばかり歌ったから失敗したのであります。私は琴にその楽想を選ぶことを任せて、琴が伯牙か伯牙が琴か、ほんとうに自分にもわかりませんでした。」と。
この物語は芸術鑑賞の極意をよく説明している。傑作というものはわれわれの心琴にかなでる一種の交響楽である。真の芸術は伯牙であり、われわれは竜門の琴である。美の霊手に触れる時、わが心琴の神秘の弦は目ざめ、われわれはこれに呼応して振動し、肉をおどらせ血をわかす。心は心と語る。無言のものに耳を傾け、見えないものを凝視する。名匠はわれわれの知らぬ調べを呼び起こす。長く忘れていた追憶はすべて新しい意味をもってかえって来る。恐怖におさえられていた希望や、認める勇気のなかった憧憬が、栄えばえと現われて来る。わが心は画家の絵の具を塗る画布である。その色素はわれわれの感情である。その濃淡の配合は、喜びの光であり悲しみの影である。われわれは傑作によって存するごとく、傑作はわれわれによって存する。
美術鑑賞に必要な同情ある心の交通は、互譲の精神によらなければならない。美術家は通信を伝える道を心得ていなければならないように、観覧者は通信を受けるに適当な態度を養わなければならない。宗匠小堀遠州は、みずから大名でありながら、次のような忘れがたい言葉を残している。「偉大な絵画に接するには、王侯に接するごとくせよ。」傑作を理解しようとするには、その前に身を低うして息を殺し、一言一句も聞きもらさじと待っていなければならない。宋のある有名な批評家が、非常におもしろい自白をしている。「若いころには、おのが好む絵を描く名人を称揚したが、鑑識力の熟するに従って、おのが好みに適するように、名人たちが選んだ絵を好むおのれを称した。」現今、名人の気分を骨を折って研究する者が実に少ないのは、誠に歎かわしいことである。われわれは、手のつけようのない無知のために、この造作のない礼儀を尽くすことをいとう。こうして、眼前に広げられた美の饗応にもあずからないことがしばしばある。名人にはいつでもごちそうの用意があるが、われわれはただみずから味わう力がないために飢えている。
同情ある人に対しては、傑作が生きた実在となり、僚友関係のよしみでこれに引きつけられるここちがする。名人は不朽である。というのは、その愛もその憂いも、幾度も繰り返してわれわれの心に生き残って行くから。われわれの心に訴えるものは、伎倆というよりは精神であり、技術というよりも人物である。呼び声が人間味のあるものであれば、それだけにわれわれの応答は衷心から出て来る。名人とわれわれの間に、この内密の黙契があればこそ詩や小説を読んで、その主人公とともに苦しみ共に喜ぶのである。わが国の沙翁近松は劇作の第一原則の一つとして、見る人に作者の秘密を打ち明かす事が重要であると定めた。弟子たちの中には幾人も、脚本をさし出して彼の称賛を得ようとした者があったが、その中で彼がおもしろいと思ったのはただ一つであった。それは、ふたごの兄弟が、人違いのために苦しむという『まちがいつづき』に多少似ている脚本であった。近松が言うには、「これこそ、劇本来の精神をそなえている。というのは、これは見る人を考えに入れているから公衆が役者よりも多く知ることを許されている。公衆は誤りの因を知っていて、哀れにも、罪もなく運命の手におちて行く舞台の上の人々を哀れむ。」と。
大家は、東西両洋ともに、見る人を腹心の友とする手段として、暗示の価値を決して忘れなかった。傑作をうちながめる人たれか心に浮かぶ綿々たる無限の思いに、畏敬の念をおこさない者があろう。傑作はすべて、いかにも親しみあり、肝胆相照らしているではないか。これにひきかえ、現代の平凡な作品はいかにも冷ややかなものではないか。前者においては、作者の心のあたたかい流露を感じ、後者においては、ただ形式的の会釈を感ずるのみである。現代人は、技術に没頭して、おのれの域を脱することはまれである。竜門の琴を、なんのかいもなくかき鳴らそうとした楽人のごとく、ただおのれを歌うのみであるから、その作品は、科学には近かろうけれども、人情を離れること遠いのである。日本の古い俚諺に「見えはる男には惚れられぬ。」というのがある。そのわけは、そういう男の心には、愛を注いで満たすべきすきまがないからである。芸術においてもこれと等しく、虚栄は芸術家公衆いずれにおいても同情心を害することはなはだしいものである。
芸術において、類縁の精神が合一するほど世にも神聖なものはない。その会するやたちまちにして芸術愛好者は自己を超越する。彼は存在すると同時に存在しない。彼は永劫を瞥見するけれども、目には舌なく、言葉をもってその喜びを声に表わすことはできない。彼の精神は、物質の束縛を脱して、物のリズムによって動いている。かくのごとくして芸術は宗教に近づいて人間をけだかくするものである。これによってこそ傑作は神聖なものとなるのである。昔日本人が大芸術家の作品を崇敬したことは非常なものであった。茶人たちはその秘蔵の作品を守るに、宗教的秘密をもってしたから、御神龕(絹地の包みで、その中へやわらかに包んで奥の院が納めてある)まで達するには、幾重にもある箱をすっかり開かねばならないことがしばしばあった。その作品が人目にふれることはきわめてまれで、しかも奥義を授かった人にのみ限られていた。
茶道の盛んであった時代においては、太閤の諸将は戦勝の褒美として、広大な領地を賜わるよりも、珍しい美術品を贈られることを、いっそう満足に思ったものであった。わが国で人気ある劇の中には、有名な傑作の喪失回復に基づいて書いたものが多い。たとえば、ある劇にこういう話がある。細川侯の御殿には雪村の描いた有名な達磨があったが、その御殿が、守りの侍の怠慢から火災にかかった。侍は万事を賭して、この宝を救い出そうと決心して、燃える御殿に飛び入って、例の掛け物をつかんだ、が、見ればはや、火炎にさえぎられて、のがれる道はなかったのである。彼は、ただその絵のことのみを心にかけて、剣をもっておのが肉を切り開き、裂いた袖に雪村を包んで、大きく開いた傷口にこれを突っ込んだ。火事はついにしずまった。煙る余燼の中に、半焼の死骸があった。その中に、火の災いをこうむらないで、例の宝物は納まっていた。実に身の毛もよだつ物語であるが、これによって、信頼を受けた侍の忠節はもちろんのこと、わが国人がいかに傑作品を重んじるかということが説明される。
しかしながら、美術の価値はただそれがわれわれに語る程度によるものであることを忘れてはならない。その言葉は、もしわれわれの同情が普遍的であったならば、普遍的なものであるかもしれない。が、われわれの限定せられた性質、代々相伝の本性はもちろんのこと、慣例、因襲の力は美術鑑賞力の範囲を制限するものである。われらの個性さえも、ある意味においてわれわれの理解力に制限を設けるものである。そして、われらの審美的個性は、過去の創作品の中に自己の類縁を求める。もっとも、修養によって美術鑑賞力は増大するものであって、われわれはこれまでは認められなかった多くの美の表現を味わうことができるようになるものである。が、畢竟するところ、われわれは万有の中に自分の姿を見るに過ぎないのである。すなわちわれら特有の性質がわれらの理解方式を定めるのである。茶人たちは全く各人個々の鑑賞力の及ぶ範囲内の物のみを収集した。
これに連関して小堀遠州に関する話を思い出す。遠州はかつてその門人たちから、彼が収集する物の好みに現われている立派な趣味を、お世辞を言ってほめられた。「どのお品も、実に立派なもので、人皆嘆賞おくあたわざるところであります。これによって先生は、利休にもまさる趣味をお持ちになっていることがわかります。というのは、利休の集めた物は、ただ千人に一人しか真にわかるものがいなかったのでありますから。」と。遠州は歎じて、「これはただいかにも自分が凡俗であることを証するのみである。偉い利休は、自分だけにおもしろいと思われる物をのみ愛好する勇気があったのだ。しかるに私は、知らず知らず一般の人の趣味にこびている。実際、利休は千人に一人の宗匠であった。」と答えた。
実に遺憾にたえないことには、現今美術に対する表面的の熱狂は、真の感じに根拠をおいていない。われわれのこの民本主義の時代においては、人は自己の感情には無頓着に世間一般から最も良いと考えられている物を得ようとかしましく騒ぐ。高雅なものではなくて、高価なものを欲し、美しいものではなくて、流行品を欲するのである。一般民衆にとっては、彼らみずからの工業主義の尊い産物である絵入りの定期刊行物をながめるほうが、彼らが感心したふりをしている初期のイタリア作品や、足利時代の傑作よりも美術鑑賞の糧としてもっと消化しやすいであろう。彼らにとっては、作品の良否よりも美術家の名が重要である。数世紀前、シナのある批評家の歎じたごとく、世人は耳によって絵画を批評する。今日いずれの方面を見ても、擬古典的嫌悪を感ずるのは、すなわちこの真の鑑賞力の欠けているためである。
なお一つ一般に誤っていることは、美術と考古学の混同である。古物から生ずる崇敬の念は、人間の性質の中で最もよい特性であって、いっそうこれを涵養したいものである。古の大家は、後世啓発の道を開いたことに対して、当然尊敬をうくべきである。彼らは幾世紀の批評を経て、無傷のままわれわれの時代に至り、今もなお光栄を荷のうているというだけで、われわれは彼らに敬意を表している。が、もしわれわれが、彼らの偉業を単に年代の古きゆえをもって尊んだとしたならば、それは実に愚かなことである。しかもわれわれは、自己の歴史的同情心が、審美的眼識を無視するままに許している。美術家が無事に墳墓におさめられると、われわれは称賛の花を手向けるのである。進化論の盛んであった十九世紀には、人類のことを考えて個人を忘れる習慣が作られた。収集家は一時期あるいは一派を説明する資料を得んことを切望して、ただ一個の傑作がよく、一定の時期あるいは一派のいかなる多数の凡俗な作にもまさって、われわれを教えるものであるということを忘れている。われわれはあまりに分類し過ぎて、あまりに楽しむことが少ない。いわゆる科学的方法の陳列のために、審美的方法を犠牲にしたことは、これまで多くの博物館の害毒であった。
同時代美術の要求は、人生の重要な計画において、いかなるものにもこれを無視することはできない。今日の美術は真にわれわれに属するものである、それはわれわれみずからの反映である。これを罵倒する時は、ただ自己を罵倒するのである。今の世に美術無し、というが、これが責めを負うべき者はたれぞ。古人に対しては、熱狂的に嘆賞するにもかかわらず、自己の可能性にはほとんど注意しないことは恥ずべきことである。世に認められようとして苦しむ美術家たち、冷たき軽侮の影に逡巡している疲れた人々よ! などというが、この自己本位の世の中に、われわれは彼らに対してどれほどの鼓舞激励を与えているか。過去がわれらの文化の貧弱を哀れむのも道理である。未来はわが美術の貧弱を笑うであろう。われわれは人生の美しい物を破壊することによって美術を破壊している。ねがわくは、ある大妖術者が出現して、社会の幹から、天才の手に触れて始めて鳴り渡る弦をそなえた大琴を作らんことを祈る。
第六章 花
春の東雲のふるえる薄明に、小鳥が木の間で、わけのありそうな調子でささやいている時、諸君は彼らがそのつれあいに花のことを語っているのだと感じたことはありませんか。人間について見れば、花を観賞することはどうも恋愛の詩と時を同じくして起こっているようである。無意識のゆえに麗しく、沈黙のために芳しい花の姿でなくて、どこに処女の心の解ける姿を想像することができよう。原始時代の人はその恋人に初めて花輪をささげると、それによって獣性を脱した。彼はこうして、粗野な自然の必要を超越して人間らしくなった。彼が不必要な物の微妙な用途を認めた時、彼は芸術の国に入ったのである。
喜びにも悲しみにも、花はわれらの不断の友である。花とともに飲み、共に食らい、共に歌い、共に踊り、共に戯れる。花を飾って結婚の式をあげ、花をもって命名の式を行なう。花がなくては死んでも行けぬ。百合の花をもって礼拝し、蓮の花をもって冥想に入り、ばらや菊花をつけ、戦列を作って突撃した。さらに花言葉で話そうとまで企てた。花なくてどうして生きて行かれよう。花を奪われた世界を考えてみても恐ろしい。病める人の枕べに非常な慰安をもたらし、疲れた人々の闇の世界に喜悦の光をもたらすものではないか。その澄みきった淡い色は、ちょうど美しい子供をしみじみながめていると失われた希望が思い起こされるように、失われようとしている宇宙に対する信念を回復してくれる。われらが土に葬られる時、われらの墓辺を、悲しみに沈んで低徊するものは花である。
悲しいかな、われわれは花を不断の友としながらも、いまだ禽獣の域を脱することあまり遠くないという事実をおおうことはできぬ。羊の皮をむいて見れば、心の奥の狼はすぐにその歯をあらわすであろう。世間で、人間は十で禽獣、二十で発狂、三十で失敗、四十で山師、五十で罪人といっている。たぶん人間はいつまでも禽獣を脱しないから罪人となるのであろう。飢渇のほか何物もわれわれに対して真実なものはなく、われらみずからの煩悩のほか何物も神聖なものはない。神社仏閣は、次から次へとわれらのまのあたり崩壊して来たが、ただ一つの祭壇、すなわちその上で至高の神へ香を焚く「おのれ」という祭壇は永遠に保存せられている。われらの神は偉いものだ。金銭がその予言者だ! われらは神へ奉納するために自然を荒らしている物質を征服したと誇っているが、物質こそわれわれを奴隷にしたものであるということは忘れている。われらは教養や風流に名をかりて、なんという残忍非道を行なっているのであろう!
星の涙のしたたりのやさしい花よ、園に立って、日の光や露の玉をたたえて歌う蜜蜂に、会釈してうなずいている花よ、お前たちは、お前たちを待ち構えている恐ろしい運命を承知しているのか。夏のそよ風にあたって、そうしていられる間、いつまでも夢を見て、風に揺られて浮かれ気分で暮らすがよい。あすにも無慈悲な手が咽喉を取り巻くだろう。お前はよじ取られて手足を一つ一つ引きさかれ、お前の静かな家から連れて行ってしまわれるだろう。そのあさましの者はすてきな美人であるかもしれぬ。そして、お前の血でその女の指がまだ湿っている間は、「まあなんて美しい花だこと。」というかもしれぬ。だがね、これが親切なことだろうか。お前が、無情なやつだと承知している者の髪の中に閉じ込められたり、もしお前が人間であったらまともに見向いてくれそうにもない人のボタン穴にさされたりするのが、お前の宿命なのかもしれない。何か狭い器に監禁せられて、ただわずかのたまり水によって、命の衰え行くのを警告する狂わんばかりの渇を止めているのもお前の運命なのかもしれぬ。
花よ、もし御門の国にいるならば、鋏と小鋸に身を固めた恐ろしい人にいつか会うかもしれぬ。その人はみずから「生花の宗匠」と称している。彼は医者の権利を要求する。だから、自然彼がきらいになるだろう。というのは、医者というものはその犠牲になった人のわずらいをいつも長びかせようとする者だからね。彼はお前たちを切ってかがめゆがめて、彼の勝手な考えでお前たちの取るべき姿勢をきめて、途方もない変な姿にするだろう。もみ療治をする者のようにお前たちの筋肉を曲げ、骨を違わせるだろう。出血を止めるために灼熱した炭でお前たちを焦がしたり、循環を助けるためにからだの中へ針金をさし込むこともあろう。塩、酢、明礬、時には硫酸を食事に与えることもあろう。お前たちは今にも気絶しそうな時に、煮え湯を足に注がれることもあろう。彼の治療を受けない場合に比べると、二週間以上も長くお前たちの体内に生命を保たせておくことができるのを彼は誇りとしているだろう。お前たちは初めて捕えられた時、その場で殺されたほうがよくはなかったか。いったいお前は前世でどんな罪を犯したとて、現世でこんな罰を当然受けねばならないのか。
西洋の社会における花の浪費は東洋の宗匠の花の扱い方よりもさらに驚き入ったものである。舞踏室や宴会の席を飾るために日々切り取られ、翌日は投げ捨てられる花の数はなかなか莫大なものに違いない。いっしょにつないだら一大陸を花輪で飾ることもできよう。このような、花の命を全く物とも思わぬことに比ぶれば、花の宗匠の罪は取るに足らないものである。彼は少なくとも自然の経済を重んじて、注意深い慮りをもってその犠牲者を選び、死後はその遺骸に敬意を表する。西洋においては、花を飾るのは富を表わす一時的美観の一部、すなわちその場の思いつきであるように思われる。これらの花は皆その騒ぎの済んだあとはどこへ行くのであろう。しおれた花が無情にも糞土の上に捨てられているのを見るほど、世にも哀れなものはない。
どうして花はかくも美しく生まれて、しかもかくまで薄命なのであろう。虫でも刺すことができる。最も温順な動物でも追いつめられると戦うものである。ボンネットを飾るために羽毛をねらわれている鳥はその追い手から飛び去ることができる、人が上着にしたいとむさぼる毛皮のある獣は、人が近づけば隠れることができる。悲しいかな! 翼ある唯一の花と知られているのは蝶であって、他の花は皆、破壊者に会ってはどうすることもできない。彼らが断末魔の苦しみに叫んだとても、その声はわれらの無情の耳へは決して達しない。われわれは、黙々としてわれらに仕えわれらを愛する人々に対して絶えず残忍であるが、これがために、これらの最もよき友からわれわれが見捨てられる時が来るかもしれない。諸君は、野生の花が年々少なくなってゆくのに気はつきませんか。それは彼らの中の賢人どもが、人がもっと人情のあるようになるまでこの世から去れと彼らに言ってきかせたのかもしれない。たぶん彼らは天へ移住してしまったのであろう。
草花を作る人のためには大いに肩を持ってやってもよい。植木鉢をいじる人は花鋏の人よりもはるかに人情がある。彼が水や日光について心配したり、寄生虫を相手に争ったり、霜を恐れたり、芽の出ようがおそい時は心配し、葉に光沢が出て来ると有頂天になって喜ぶ様子をうかがっているのは楽しいものである。東洋では花卉栽培の道は非常に古いものであって、詩人の嗜好とその愛好する花卉はしばしば物語や歌にしるされている。唐宋の時代には陶器術の発達に伴なって、花卉を入れる驚くべき器が作られたということである。といっても植木鉢ではなく宝石をちりばめた御殿であった。花ごとに仕える特使が派遣せられ、兎の毛で作ったやわらかい刷毛でその葉を洗うのであった。牡丹は、盛装した美しい侍女が水を与うべきもの、寒梅は青い顔をしてほっそりとした修道僧が水をやるべきものと書いた本がある。日本で、足利時代に作られた「鉢の木」という最も通俗な能の舞は、貧困な武士がある寒夜に炉に焚く薪がないので、旅僧を歓待するために、だいじに育てた鉢の木を切るという話に基づいて書いたものである。その僧とは実はわが物語のハルンアルラシッド(三一)ともいうべき北条時頼にほかならなかった。そしてその犠牲に対しては報酬なしではなかった。この舞は現今でも必ず東京の観客の涙を誘うものである。
か弱い花を保護するためには、非常な警戒をしたものであった。唐の玄宗皇帝は、鳥を近づけないために花園の樹枝に小さい金の鈴をかけておいた。春の日に宮廷の楽人を率いていで、美しい音楽で花を喜ばせたのも彼であった。わが国のアーサー王物語の主人公ともいうべき、義経の書いたものだという伝説のある、奇妙な高札が日本のある寺院(須磨寺)に現存している。それはある不思議な梅の木を保護するために掲げられた掲示であって、尚武時代のすごいおかしみをもってわれらの心に訴える。梅花の美しさを述べた後「一枝を伐らば一指を剪るべし。」という文が書いてある。花をむやみに切り捨てたり、美術品をばだいなしにする者どもに対しては、今日においてもこういう法律が願わくは実施せられよかしと思う。
しかし鉢植えの花の場合でさえ、人間の勝手気ままな事が感ぜられる気がする。何ゆえに花をそのふるさとから連れ出して、知らぬ他郷に咲かせようとするのであるか。それは小鳥を籠に閉じこめて、歌わせようとするのも同じではないか。蘭類が温室で、人工の熱によって息づまる思いをしながら、なつかしい南国の空を一目見たいとあてもなくあこがれているとだれが知っていよう。
花を理想的に愛する人は、破れた籬の前に座して野菊と語った陶淵明や、たそがれに、西湖の梅花の間を逍遙しながら、暗香浮動の趣に我れを忘れた林和靖のごとく、花の生まれ故郷に花をたずねる人々である。周茂叔は、彼の夢が蓮の花の夢と混ずるように、舟中に眠ったと伝えられている。この精神こそは奈良朝で有名な光明皇后のみ心を動かしたものであって、「折りつればたぶさにけがるたてながら三世の仏に花たてまつる(三二)。」とお詠みになった。
しかしあまりに感傷的になることはやめよう。奢る事をいっそういましめて、もっと壮大な気持ちになろうではないか。老子いわく「天地不仁(三三)。」弘法大師いわく「生まれ生まれ生まれ生まれて生の始めに暗く、死に死に死に死んで死の終わりに冥し(三四)。」われわれはいずれに向かっても「破壊」に面するのである。上に向かうも破壊、下に向かうも破壊、前にも破壊、後ろにも破壊。変化こそは唯一の永遠である。何ゆえに死を生のごとく喜び迎えないのであるか。この二者はただ互いに相対しているものであって、梵(三五)の昼と夜である。古きものの崩解によって改造が可能となる。われわれは、無情な慈悲の神「死」をば種々の名前であがめて来た。拝火教徒が火中に迎えたものは、「すべてを呑噬するもの」の影であった。今日でも、神道の日本人がその前にひれ伏すところのものは、剣魂の氷のような純潔である。神秘の火はわれらの弱点を焼きつくし、神聖な剣は煩悩のきずなを断つ。われらの屍灰の中から天上の望みという不死の鳥が現われ、煩悩を脱していっそう高い人格が生まれ出て来る。
花をちぎる事によって、新たな形を生み出して世人の考えを高尚にする事ができるならば、そうしてもよいではないか。われわれが花に求むるところはただ美に対する奉納を共にせん事にあるのみ。われわれは「純潔」と「清楚」に身をささげる事によってその罪滅ぼしをしよう。こういうふうな論法で、茶人たちは生花の法を定めたのである。
わが茶や花の宗匠のやり口を知っている人はだれでも、彼らが宗教的の尊敬をもって花を見る事に気がついたに違いない。彼らは一枝一条もみだりに切り取る事をしないで、おのが心に描く美的配合を目的に注意深く選択する。彼らは、もし絶対に必要の度を越えて万一切り取るようなことがあると、これを恥とした。これに関連して言ってもよろしいと思われる事は、彼らはいつも、多少でも葉があればこれを花に添えておくという事である。というのは、彼らの目的は花の生活の全美を表わすにあるから。この点については、その他の多くの点におけると同様、彼らの方法は西洋諸国に行なわれるものとは異なっている。かの国では、花梗のみ、いわば胴のない頭だけが乱雑に花瓶にさしこんであるのをよく見受ける。
茶の宗匠が花を満足に生けると、彼はそれを日本間の上座にあたる床の間に置く。その効果を妨げるような物はいっさいその近くにはおかない。たとえば一幅の絵でも、その配合に何か特殊の審美的理由がなければならぬ。花はそこに王位についた皇子のようにすわっている、そして客やお弟子たちは、その室に入るやまずこれに丁寧なおじぎをしてから始めて主人に挨拶をする。生花の傑作を写した絵が素人のために出版せられている。この事に関する文献はかなり大部なものである。花が色あせると宗匠はねんごろにそれを川に流し、または丁寧に地中に埋める。その霊を弔って墓碑を建てる事さえもある。
花道の生まれたのは十五世紀で、茶の湯の起こったのと同時らしく思われる。わが国の伝説によると、始めて花を生けたのは昔の仏教徒であると言う。彼らは生物に対する限りなき心やりのあまり、暴風に散らされた花を集めて、それを水おけに入れたということである。足利義政時代の大画家であり、鑑定家である相阿弥は、初期における花道の大家の一人であったといわれている。茶人珠光はその門人であった。また絵画における狩野家のように、花道の記録に有名な池の坊の家元専能もこの人の門人であった。十六世紀の後半において、利休によって茶道が完成せられるとともに、生花も充分なる発達を遂げた。利休およびその流れをくんだ有名な織田有楽、古田織部、光悦、小堀遠州、片桐石州らは新たな配合を作ろうとして互いに相競った。しかし茶人たちの花の尊崇は、ただ彼らの審美的儀式の一部をなしたに過ぎないのであって、それだけが独立して、別の儀式をなしてはいなかったという事を忘れてはならぬ。生花は茶室にある他の美術品と同様に、装飾の全配合に従属的なものであった。ゆえに石州は「雪が庭に積んでいる時は白い梅花を用いてはならぬ。」と規定した。「けばけばしい」花は無情にも茶室から遠ざけられた。茶人の生けた生花はその本来の目的の場所から取り去ればその趣旨を失うものである。と言うのは、その線やつり合いは特にその周囲のものとの配合を考えてくふうしてあるのであるから。
花を花だけのために崇拝する事は、十七世紀の中葉、花の宗匠が出るようになって起こったのである。そうなると茶室には関係なく、ただ花瓶が課する法則のほかには全く法則がなくなった。新しい考案、新しい方法ができるようになって、これらから生まれ出た原則や流派がたくさんあった。十九世紀のある文人の言うところによれば、百以上の異なった生花の流派をあげる事ができる。広く言えばこれら諸流は、形式派と写実派の二大流派に分かれる。池の坊を家元とする形式派は、狩野派に相当する古典的理想主義をねらっていた。初期のこの派の宗匠の生花の記録があるが、それは山雪や常信の花の絵をほとんどそのままにうつし出したものである。一方写実派はその名の示すごとく、自然をそのモデルと思って、ただ美的調和を表現する助けとなるような形の修正を加えただけである。ゆえにこの派の作には浮世絵や四条派の絵をなしている気分と同じ気分が認められる。
時の余裕があれば、この時代の幾多の花の宗匠の定めた生花の法則になお詳細に立ち入って、徳川時代の装飾を支配していた根本原理を明らかにすること(そうすれば明らかになると思われるが)は興味あることであろう。彼らは導く原理(天)、従う原理(地)、和の原理(人)のことを述べている、そしてこれらの原理をかたどらない生花は没趣味な死んだ花であると考えられた。また花を、正式、半正式、略式の三つの異なった姿に生ける必要を詳述している。第一は舞踏場へ出るものものしい服装をした花の姿を現わし、第二はゆったりとした趣のある午後服の姿を現わし、第三は閨房にある美しい平常着の姿を現わすともいわれよう。
われらは花の宗匠の生花よりも茶人の生花に対してひそかに同情を持つ。茶人の花は、適当に生けると芸術であって、人生と真に密接な関係を持っているからわれわれの心に訴えるのである。この流派を、写実派および形式派と対称区別して、自然派と呼びたい。茶人たちは、花を選択することでかれらのなすべきことは終わったと考えて、その他のことは花みずからの身の上話にまかせた。晩冬のころ茶室に入れば、野桜の小枝につぼみの椿の取りあわせてあるのを見る。それは去らんとする冬のなごりときたらんとする春の予告を配合したものである。またいらいらするような暑い夏の日に、昼のお茶に行って見れば、床の間の薄暗い涼しい所にかかっている花瓶には、一輪の百合を見るであろう。露のしたたる姿は、人生の愚かさを笑っているように思われる。
花の独奏はおもしろいものであるが、絵画、彫刻の協奏曲となれば、その取りあわせには人を恍惚とさせるものがある。石州はかつて湖沼の草木を思わせるように水盤に水草を生けて、上の壁には相阿弥の描いた鴨の空を飛ぶ絵をかけた。紹巴という茶人は、海辺の野花と漁家の形をした青銅の香炉に配するに、海岸のさびしい美しさを歌った和歌をもってした。その客人の一人は、その全配合の中に晩秋の微風を感じたとしるしている。
花物語は尽きないが、もう一つだけ語ることにしよう。十六世紀には、朝顔はまだわれわれに珍しかった。利休は庭全体にそれを植えさせて、丹精こめて培養した。利休の朝顔の名が太閤のお耳に達すると太閤はそれを見たいと仰せいだされた。そこで利休はわが家の朝の茶の湯へお招きをした。その日になって太閤は庭じゅうを歩いてごらんになったが、どこを見ても朝顔のあとかたも見えなかった。地面は平らかにして美しい小石や砂がまいてあった。その暴君はむっとした様子で茶室へはいった。しかしそこにはみごとなものが待っていて彼のきげんは全くなおって来た。床の間には宋細工の珍しい青銅の器に、全庭園の女王である一輪の朝顔があった。
こういう例を見ると、「花御供」の意味が充分にわかる。たぶん花も充分にその真の意味を知るであろう。彼らは人間のような卑怯者ではない。花によっては死を誇りとするものもある。たしかに日本の桜花は、風に身を任せて片々と落ちる時これを誇るものであろう。吉野や嵐山のかおる雪崩の前に立ったことのある人は、だれでもきっとそう感じたであろう。宝石をちりばめた雲のごとく飛ぶことしばし、また水晶の流れの上に舞い、落ちては笑う波の上に身を浮かべて流れながら「いざさらば春よ、われらは永遠の旅に行く。」というようである。
第七章 茶の宗匠
宗教においては未来がわれらの背後にある。芸術においては現在が永遠である。茶の宗匠の考えによれば芸術を真に鑑賞することは、ただ芸術から生きた力を生み出す人々にのみ可能である。ゆえに彼らは茶室において得た風流の高い軌範によって彼らの日常生活を律しようと努めた。すべての場合に心の平静を保たねばならぬ、そして談話は周囲の調和を決して乱さないように行なわなければならぬ。着物の格好や色彩、身体の均衡や歩行の様子などすべてが芸術的人格の表現でなければならぬ。これらの事がらは軽視することのできないものであった。というのは、人はおのれを美しくして始めて美に近づく権利が生まれるのであるから。かようにして宗匠たちはただの芸術家以上のものすなわち芸術そのものとなろうと努めた。それは審美主義の禅であった。われらに認めたい心さえあれば完全は至るところにある。利休は好んで次の古歌を引用した。
花をのみ待つらん人に山里の雪間の草の春を見せばや(三六)
茶の宗匠たちの芸術に対する貢献は実に多方面にわたっていた。彼らは古典的建築および屋内の装飾を全く革新して、前に茶室の章で述べた新しい型を確立した。その影響は十六世紀以後に建てられた宮殿寺院さえも皆これをうけている。多能な小堀遠州は、桂の離宮、名古屋の城および孤篷庵に、彼が天才の著名な実例をのこしている。日本の有名な庭園は皆茶人によって設計せられたものである。わが国の陶器はもし彼らが鼓舞を与えてくれなかったら、優良な品質にはたぶんならなかったであろう。茶の湯に用いられた器具の製造のために、製陶業者のほうではあらん限りの新くふうの知恵を絞ったのであった。遠州の七窯は日本の陶器研究者の皆よく知っているところである。わが国の織物の中には、その色彩や意匠を考案した宗匠の名を持っているものが多い。実際、芸術のいかなる方面にも、茶の宗匠がその天才の跡をのこしていないところはない。絵画、漆器に関しては彼らの尽くした莫大の貢献についていうのはほとんど贅言と思われる。絵画の一大派はその源を、茶人であり同時にまた塗師、陶器師として有名な本阿弥光悦に発している。彼の作品に比すれば、その孫の光甫や甥の子光琳および乾山の立派な作もほとんど光を失うのである。いわゆる光琳派はすべて、茶道の表現である。この派の描く太い線の中に、自然そのものの生気が存するように思われる。
茶の宗匠が芸術界に及ぼした影響は偉大なものではあったが、彼らが処世上に及ぼした影響の大なるに比すれば、ほとんど取るに足らないものである。上流社会の慣例におけるのみならず、家庭の些事の整理に至るまで、われわれは茶の宗匠の存在を感ずるのである。配膳法はもとより、美味の膳部の多くは彼らの創案したものである。彼らは落ち着いた色の衣服をのみ着用せよと教えた。また生花に接する正しい精神を教えてくれた。彼らは、人間は生来簡素を愛するものであると強調して、人情の美しさを示してくれた。実際、彼らの教えによって茶は国民の生活の中にはいったのである。
この人生という、愚かな苦労の波の騒がしい海の上の生活を、適当に律してゆく道を知らない人々は、外観は幸福に、安んじているようにと努めながらも、そのかいもなく絶えず悲惨な状態にいる。われわれは心の安定を保とうとしてはよろめき、水平線上に浮かぶ雲にことごとく暴風雨の前兆を見る。しかしながら、永遠に向かって押し寄せる波濤のうねりの中に、喜びと美しさが存している。何ゆえにその心をくまないのであるか、また列子のごとく風そのものに御しないのであるか。
美を友として世を送った人のみが麗しい往生をすることができる。大宗匠たちの臨終はその生涯と同様に絶妙都雅なものであった。彼らは常に宇宙の大調和と和しようと努め、いつでも冥土へ行くの覚悟をしていた。利休の「最後の茶の湯」は悲壮の極として永久にかがやくであろう。
利休と太閤秀吉との友誼は長いものであって、この偉大な武人が茶の宗匠を尊重したことも非常なものであった。しかし暴君の友誼はいつも危険な光栄である。その時代は不信にみちた時代であって、人は近親の者さえも信頼しなかった。利休は媚びへつらう佞人ではなかったから、恐ろしい彼の後援者と議論して、しばしば意見を異にするをもはばからなかった。太閤と利休の間にしばらく冷ややかな感情のあったのを幸いに、利休を憎む者どもは利休がその暴君を毒害しようとする一味の連累であると言った。宗匠のたてる一碗の緑色飲料とともに、命にかかわる毒薬が盛られることになっているということが、ひそかに秀吉の耳にはいった。秀吉においては、嫌疑があるというだけでも即時死刑にする充分な理由であった、そしてその怒れる支配者の意に従うよりほかに哀訴の道もなかったのである。死刑囚にただ一つの特権が許された、すなわち自害するという光栄である。
利休が自己犠牲をすることに定められた日に、彼はおもなる門人を最後の茶の湯に招いた。客は悲しげに定刻待合に集まった。庭径をながむれば樹木も戦慄するように思われ、木の葉のさらさらとそよぐ音にも、家なき亡者の私語が聞こえる。地獄の門前にいるまじめくさった番兵のように、灰色の燈籠が立っている。珍香の香が一時に茶室から浮動して来る。それは客にはいれとつげる招きである。一人ずつ進み出ておのおのその席につく。床の間には掛け物がかかっている、それは昔ある僧の手になった不思議な書であって浮世のはかなさをかいたものである。火鉢にかかって沸いている茶釜の音には、ゆく夏を惜しみ悲痛な思いを鳴いている蝉の声がする。やがて主人が室に入る。おのおの順次に茶をすすめられ、順次に黙々としてこれを飲みほして、最後に主人が飲む。定式に従って、主賓がそこでお茶器拝見を願う。利休は例の掛け物とともにいろいろな品を客の前におく。皆の者がその美しさをたたえて後、利休はその器を一つずつ一座の者へ形見として贈る。茶わんのみは自分でとっておく。「不幸の人のくちびるによって不浄になった器は決して再び人間には使用させない。」と言ってかれはこれをなげうって粉砕する。
その式は終わった、客は涙をおさえかね、最後の訣別をして室を出て行く。彼に最も親密な者がただ一人、あとに残って最期を見届けてくれるようにと頼まれる。そこで利休は茶会の服を脱いで、だいじにたたんで畳の上におく、それでその時まで隠れていた清浄無垢な白い死に装束があらわれる。彼は短剣の輝く刀身を恍惚とながめて、次の絶唱を詠む。
人生七十 力囲希咄 吾が這の宝剣 祖仏共に殺す(三七)
笑みを顔にうかべながら、利休は冥土へ行ったのであった。
「茶の本」岩波文庫
1929(昭和4)年3月10日 第1刷発行
- ハルンアルラシッド ―― 『アラビアン・ナイト』(千一夜物語)の主人公。
- 後撰集に僧正遍昭作として同様のものがある。なお、為頼朝臣集に「折りつれば心もけがるもとながら今の仏にはな奉る」とあり、光明皇后の御詠として「わがために花は手折らじされどただ三世の諸仏の前にささげん」としたものもある。
- 「天地不仁。」 ―― 原文は「仁とせず」あるいは「不仁ならんや」と読む人もあるがここには「仁ならず」として引用してある。
- 大師作、『秘蔵宝鑰』の序より。
- 梵 ―― インドの波羅門教における最高原理。
- 花をのみ…… ―― 藤原家隆作。利休はわびの本意とてこの歌を常に吟じておったとのことである。
- 人生七十力囲希咄。吾が這の宝剣祖仏共に殺す ―― 人生七十 力囲希咄 吾這宝剣 祖仏共殺。「力囲希咄」を「リキイキトツ」と読むのは、元禄十五年出版の、河東散人鷯巣が藤村庸軒の説話を筆録したという「茶話指月集」の読み方によったものである。意味は徳川時代から茶人の間の問題となっていて、諸説紛々。今泉雄作氏の説では、禅の喝のような一種の間投詞で、「ええなんじゃいの」といった意味であるとのこと。京都表千家に伝えられている利休の真蹟には「人世」、力㘞となっている由である。また「禅林僧室伝」巻三、雲門文偃章下に、雲門偈ニ云ク、咄咄咄力㘞希禅子訝ル中眉垂ルとある。英文には、この語句の意味を思わせるところは表われていない。
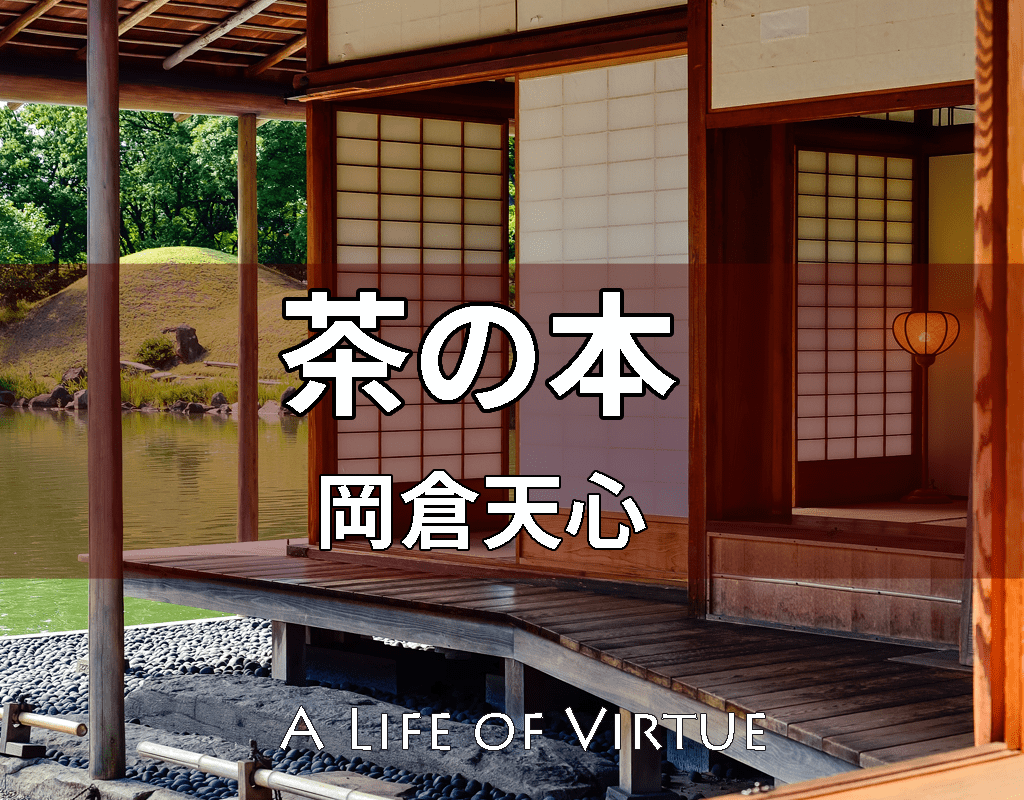 p.4
p.4