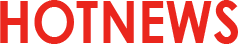第一章 人情の碗
茶は薬用として始まり後飲料となる。シナにおいては八世紀に高雅な遊びの一つとして詩歌の域に達した。十五世紀に至り日本はこれを高めて一種の審美的宗教、すなわち茶道にまで進めた。茶道は日常生活の俗事の中に存する美しきものを崇拝することに基づく一種の儀式であって、純粋と調和、相互愛の神秘、社会秩序のローマン主義を諄々と教えるものである。茶道の要義は「不完全なもの」を崇拝するにある。いわゆる人生というこの不可解なもののうちに、何か可能なものを成就しようとするやさしい企てであるから。
茶の原理は普通の意味でいう単なる審美主義ではない。というのは、倫理、宗教と合して、天人に関するわれわれのいっさいの見解を表わしているものであるから。それは衛生学である、清潔をきびしく説くから。それは経済学である、というのは、複雑なぜいたくというよりもむしろ単純のうちに慰安を教えるから。それは精神幾何学である、なんとなれば、宇宙に対するわれわれの比例感を定義するから。それはあらゆるこの道の信者を趣味上の貴族にして、東洋民主主義の真精神を表わしている。
日本が長い間世界から孤立していたのは、自省をする一助となって茶道の発達に非常に好都合であった。われらの住居、習慣、衣食、陶漆器、絵画等 ――文学でさえも―― すべてその影響をこうむっている。いやしくも日本の文化を研究せんとする者は、この影響の存在を無視することはできない。茶道の影響は貴人の優雅な閨房にも、下賤の者の住み家にも行き渡ってきた。わが田夫は花を生けることを知り、わが野人も山水を愛でるに至った。俗に「あの男は茶気がない」という。もし人が、わが身の上におこるまじめながらの滑稽を知らないならば。また浮世の悲劇にとんじゃくもなく、浮かれ気分で騒ぐ半可通を「あまり茶気があり過ぎる」と言って非難する。
よその目には、つまらぬことをこのように騒ぎ立てるのが、実に不思議に思われるかもしれぬ。一杯のお茶でなんという騒ぎだろうというであろうが、考えてみれば、煎ずるところ人間享楽の茶碗は、いかにも狭いものではないか、いかにも早く涙であふれるではないか、無辺を求むる渇のとまらぬあまり、一息に飲みほされるではないか。してみれば、茶碗をいくらもてはやしたとてとがめだてには及ぶまい。人間はこれよりもまだまだ悪いことをした。酒の神バッカスを崇拝するのあまり、惜しげもなく奉納をし過ぎた。軍神マーズの血なまぐさい姿をさえも理想化した。してみれば、カメリヤの女皇に身をささげ、その祭壇から流れ出る暖かい同情の流れを、心ゆくばかり楽しんでもよいではないか。象牙色の磁器にもられた液体琥珀の中に、その道の心得ある人は、孔子の心よき沈黙、老子の奇警、釈迦牟尼の天上の香にさえ触れることができる。
おのれに存する偉大なるものの小を感ずることのできない人は、他人に存する小なるものの偉大を見のがしがちである。一般の西洋人は、茶の湯を見て、東洋の珍奇、稚気をなしている千百の奇癖のまたの例に過ぎないと思って、袖の下で笑っているであろう。西洋人は、日本が平和な文芸にふけっていた間は、野蛮国と見なしていたものである。しかるに満州の戦場に大々的殺戮を行ない始めてから文明国と呼んでいる。近ごろ武士道 ――わが兵士に喜び勇んで身を捨てさせる死の術―― について盛んに論評されてきた。しかし茶道にはほとんど注意がひかれていない。この道はわが生の術を多く説いているものであるが。もしわれわれが文明国たるためには、血なまぐさい戦争の名誉によらなければならないとするならば、むしろいつまでも野蛮国に甘んじよう。われわれはわが芸術および理想に対して、しかるべき尊敬が払われる時期が来るのを喜んで待とう。
いつになったら西洋が東洋を了解するであろう、否、了解しようと努めるであろう。われわれアジア人はわれわれに関して織り出された事実や想像の妙な話にしばしば胆を冷やすことがある。われわれは、ねずみや油虫を食べて生きているのでないとしても、蓮の香を吸って生きていると思われている。これは、つまらない狂信か、さもなければ見さげ果てた逸楽である。インドの心霊性を無知といい、シナの謹直を愚鈍といい、日本の愛国心をば宿命論の結果といってあざけられていた。はなはだしきは、われわれは神経組織が無感覚なるため、傷や痛みに対して感じが薄いとまで言われていた。
西洋の諸君、われわれを種にどんなことでも言ってお楽しみなさい。アジアは返礼いたします。まだまだおもしろい種になることはいくらでもあろう、もしわれわれ諸君についてこれまで、想像したり書いたりしたことがすっかりおわかりになれば。すべて遠きものをば美しと見、不思議に対して知らず知らず感服し、新しい不分明なものに対しては、口には出さねど憤るということがそこに含まれている。諸君はこれまで、うらやましく思うこともできないほど立派な徳を負わされて、あまり美しくて、とがめることのできないような罪をきせられている。わが国の昔の文人は ――その当時の物知りであった―― まあこんなことを言っている。諸君には着物のどこか見えないところに、毛深いしっぽがあり、そしてしばしば赤ん坊の細切り料理を食べていると! 否、われわれは諸君に対してもっと悪いことを考えていた。すなわち諸君は、地球上で最も実行不可能な人種と思っていた。というわけは、諸君は決して実行しないことを口では説いているといわれていたから。
かくのごとき誤解はわれわれのうちからすみやかに消え去ってゆく。商業上の必要に迫られて欧州の国語が、東洋幾多の港に用いられるようになって来た。アジアの青年は現代的教育を受けるために、西洋の大学に群がってゆく。われわれの洞察力は、諸君の文化に深く入り込むことはできない。しかし少なくともわれわれは喜んで学ぼうとしている。私の同国人のうちには、諸君の習慣や礼儀作法をあまりに多く取り入れた者がある。こういう人は、こわばったカラや丈の高いシルクハットを得ることが、諸君の文明を得ることと心得違いをしていたのである。かかる様子ぶりは、実に哀れむべき嘆かわしいものであるが、ひざまずいて西洋文明に近づこうとする証拠となる。不幸にして、西洋の態度は東洋を理解するに都合が悪い。キリスト教の宣教師は与えるために行き、受けようとはしない。諸君の知識は、もし通りすがりの旅人のあてにならない話に基づくのでなければ、わが文学の貧弱な翻訳に基づいている。ラフカディオ・ハーンの義侠的ペン、または『インド生活の組織(一)』の著者のそれが、われわれみずからの感情の松明をもって東洋の闇を明るくすることはまれである。
私はこんなにあけすけに言って、たぶん茶道についての私自身の無知を表わすであろう。茶道の高雅な精神そのものは、人から期待せられていることだけ言うことを要求する。しかし私は立派な茶人のつもりで書いているのではない。新旧両世界の誤解によって、すでに非常な禍をこうむっているのであるから、お互いがよく了解することを助けるために、いささかなりとも貢献するに弁解の必要はない。二十世紀の初めに、もしロシアがへりくだって日本をよく了解していたら、血なまぐさい戦争の光景は見ないで済んだであろうに。東洋の問題をさげすんで度外視すれば、なんという恐ろしい結果が人類に及ぶことであろう。ヨーロッパの帝国主義は、黄禍のばかげた叫びをあげることを恥じないが、アジアもまた、白禍の恐るべきをさとるに至るかもしれないということは、わかりかねている。諸君はわれわれを「あまり茶気があり過ぎる」と笑うかもしれないが、われわれはまた西洋の諸君には天性「茶気がない」と思うかもしれないではないか。
東西両大陸が互いに奇警な批評を飛ばすことはやめにして、東西互いに得る利益によって、よし物がわかって来ないとしても、お互いにやわらかい気持ちになろうではないか。お互いに違った方面に向かって発展して来ているが、しかし互いに長短相補わない道理はない。諸君は心の落ちつきを失ってまで膨張発展を遂げた。われわれは侵略に対しては弱い調和を創造した。諸君は信ずることができますか、東洋はある点で西洋にまさっているということを!
不思議にも人情は今までのところ茶碗に東西相合している。茶道は世界的に重んぜられている唯一のアジアの儀式である。白人はわが宗教道徳を嘲笑した。しかしこの褐色飲料は躊躇もなく受け入れてしまった。午後の喫茶は、今や西洋の社会における重要な役をつとめている。盆や茶托の打ち合う微妙な音にも、ねんごろにもてなす婦人の柔らかい絹ずれの音にも、また、クリームや砂糖を勧められたり断わったりする普通の問答にも、茶の崇拝は疑いもなく確立しているということがわかる。渋いか甘いか疑わしい煎茶の味は、客を待つ運命に任せてあきらめる。この一事にも東洋精神が強く現われているということがわかる。
ヨーロッパにおける茶についての最も古い記事は、アラビヤの旅行者の物語にあると言われていて、八七九年以後広東における主要なる歳入の財源は塩と茶の税であったと述べてある。マルコポーロは、シナの市舶司が茶税を勝手に増したために、一二八五年免職になったことを記録している。ヨーロッパ人が、極東についていっそう多く知り始めたのは、実に大発見時代のころである。十六世紀の終わりにオランダ人は、東洋において灌木の葉からさわやかな飲料が造られることを報じた。ジオヴァーニ・バティスタ・ラムージオ(一五五九)、エル・アルメイダ(一五七六)、マフェノ(一五八八)、タレイラ(一六一〇)らの旅行者たちもまた茶のことを述べている(二)。一六一〇年に、オランダ東インド会社の船がヨーロッパに初めて茶を輸入した。一六三六年にはフランスに伝わり、一六三八年にはロシアにまで達した。英国は一六五〇年これを喜び迎えて、「かの卓絶せる、かつすべての医者の推奨するシナ飲料、シナ人はこれをチャと呼び、他国民はこれをテイまたはティーと呼ぶ。」と言っていた。
この世のすべてのよい物と同じく、茶の普及もまた反対にあった。ヘンリー・セイヴィル(一六七八)のような異端者は、茶を飲むことを不潔な習慣として口をきわめて非難した。ジョウナス・ハンウェイは言った。(茶の説・一七五六)茶を用いれば男は身のたけ低くなり、みめをそこない、女はその美を失うと。茶の価の高いために(一ポンド約十五シリング)初めは一般の人の消費を許さなかった。「歓待饗応用の王室御用品、王侯貴族の贈答用品」として用いられた。しかしこういう不利な立場にあるにもかかわらず、喫茶は、すばらしい勢いで広まって行った。十八世紀前半におけるロンドンのコーヒー店は、実際喫茶店となり、アディソンやスティールのような文士のつどうところとなり、茶を喫しながらかれらは退屈しのぎをしたものである。この飲料はまもなく生活の必要品 ――課税品―― となった。これに関連して、現代の歴史において茶がいかに主要な役を務めているかを思い出す。アメリカ植民地は圧迫を甘んじて受けていたが、ついに、茶の重税に堪えかねて人間の忍耐力も尽きてしまった。アメリカの独立は、ボストン港に茶箱を投じたことに始まる。
茶の味には微妙な魅力があって、人はこれに引きつけられないわけにはゆかない、またこれを理想化するようになる。西洋の茶人たちは、茶のかおりとかれらの思想の芳香を混ずるに鈍ではなかった。茶には酒のような傲慢なところがない。コーヒーのような自覚もなければ、またココアのような気取った無邪気もない。一七一一年にすでにスペクテイター紙に次のように言っている。「それゆえに私は、この私の考えを、毎朝、茶とバタつきパンに一時間を取っておかれるような、すべての立派な御家庭へ特にお勧めしたいと思います。そして、どうぞこの新聞を、お茶のしたくの一部分として、時間を守って出すようにお命じになることを、せつにお勧めいたします。」サミュエル・ジョンソンはみずからの人物を描いて次のように言っている。「因業な恥知らずのお茶飲みで、二十年間も食事を薄くするにただこの魔力ある植物の振り出しをもってした。そして茶をもって夕べを楽しみ、茶をもって真夜中を慰め、茶をもって晨を迎えた。」
ほんとうの茶人チャールズ・ラムは、「ひそかに善を行なって偶然にこれが現われることが何よりの愉快である。」というところに茶道の真髄を伝えている。というわけは、茶道は美を見いださんがために美を隠す術であり、現わすことをはばかるようなものをほのめかす術である。この道はおのれに向かって、落ち着いてしかし充分に笑うけだかい奥義である。従ってヒューマーそのものであり、悟りの微笑である。すべて真に茶を解する人はこの意味において茶人と言ってもよかろう。たとえばサッカレー、それからシェイクスピアはもちろん、文芸廃頽期の詩人もまた、(と言っても、いずれの時か廃頽期でなかろう)物質主義に対する反抗のあまりいくらか茶道の思想を受け入れた。たぶん今日においてもこの「不完全」を真摯に静観してこそ、東西相会して互いに慰めることができるであろう。
道教徒はいう、「無始」の始めにおいて「心」と「物」が決死の争闘をした。ついに大日輪黄帝は闇と地の邪神祝融に打ち勝った。その巨人は死苦のあまり頭を天涯に打ちつけ、硬玉の青天を粉砕した。星はその場所を失い、月は夜の寂寞たる天空をあてもなくさまようた。失望のあまり黄帝は、遠く広く天の修理者を求めた。捜し求めたかいはあって東方の海から女媧という女皇、角をいただき竜尾をそなえ、火の甲冑をまとって燦然たる姿で現われた。その神は不思議な大釜に五色の虹を焼き出し、シナの天を建て直した。しかしながら、また女媧は蒼天にある二個の小隙を埋めることを忘れたと言われている。かくのごとくして愛の二元論が始まった。すなわち二個の霊は空間を流転してとどまることを知らず、ついに合して始めて完全な宇宙をなす。人はおのおの希望と平和の天空を新たに建て直さなければならぬ。
現代の人道の天空は、富と権力を得んと争う莫大な努力によって全く粉砕せられている。世は利己、俗悪の闇に迷っている。知識は心にやましいことをして得られ、仁は実利のために行なわれている。東西両洋は、立ち騒ぐ海に投げ入れられた二竜のごとく、人生の宝玉を得ようとすれどそのかいもない。この大荒廃を繕うために再び女媧を必要とする。われわれは大権化の出現を待つ。まあ、茶でも一口すすろうではないか。明るい午後の日は竹林にはえ、泉水はうれしげな音をたて、松籟はわが茶釜に聞こえている。はかないことを夢に見て、美しい取りとめのないことをあれやこれやと考えようではないか。
第二章 茶の諸流
茶は芸術品であるから、その最もけだかい味を出すには名人を要する。茶にもいろいろある、絵画に傑作と駄作と ――概して後者―― があると同様に。と言っても、立派な茶をたてるのにこれぞという秘法はない、ティシアン、雪村のごとき名画を作製するのに何も規則がないと同様に。茶はたてるごとに、それぞれ個性を備え、水と熱に対する特別の親和力を持ち、世々相伝の追憶を伴ない、それ独特の話しぶりがある。真の美は必ず常にここに存するのである。芸術と人生のこの単純な根本的法則を、社会が認めないために、われわれはなんという損失をこうむっていることであろう。宋の詩人李仲光は、世に最も悲しむべきことが三つあると嘆じた、すなわち誤れる教育のために立派な青年をそこなうもの、鑑賞の俗悪なために名画の価値を減ずるもの、手ぎわの悪いために立派なお茶を全く浪費するものこれである。
芸術と同じく、茶にもその時代と流派とがある。茶の進化は概略三大時期に分けられる、煎茶、抹茶および掩茶すなわちこれである。われわれ現代人はその最後の流派に属している。これら茶のいろいろな味わい方は、その流行した当時の時代精神を表わしている。と言うのは、人生はわれらの内心の表現であり、知らず知らずの行動はわれわれの内心の絶えざる発露であるから。孔子いわく「人いずくんぞ廋さんや、人いずくんぞ廋さんや」と。たぶんわれわれは隠すべき偉大なものが非常に少ないからであろう、些事に自己を顕わすことが多すぎて困る。日々起こる小事件も、哲学、詩歌の高翔と同じく人種的理想の評論である。愛好する葡萄酒の違いでさえ、ヨーロッパのいろいろな時代や国民のそれぞれの特質を表わしているように、茶の理想もいろいろな情調の東洋文化の特徴を表わしている。煮る団茶、かき回す粉茶、淹す葉茶はそれぞれ、唐、宋、明の気分を明らかに示している。もし、芸術分類に濫用された名称を借りるとすれば、これらをそれぞれ、古典的、ローマン的、および自然主義的な茶の諸流と言えるであろう。
南シナの産なる茶の木は、ごく早い時代からシナの植物学界および薬物学界に知られていた。古典には、梌、蔎、荈、檟、茗、というようないろいろな名前で書いてあって、疲労をいやし、精神をさわやかにし、意志を強くし、視力をととのえる効能があるために大いに重んぜられた。ただに内服薬として服用せられたのみならず、しばしばリューマチの痛みを軽減するために、煉薬として外用薬にも用いられた。道教徒は、不死の霊薬の重要な成分たることを主張した。仏教徒は、彼らが長時間の黙想中に、睡魔予防剤として広くこれを服用した。
四五世紀のころには、揚子江流域住民の愛好飲料となった。このころに至って始めて、現代用いている「茶」という表意文字が造られたのである。これは明らかに、古い「※梌」の字の俗字であろう。南朝の詩人は「液体硬玉の泡沫」を熱烈に崇拝した跡が見えている。また帝王は、高官の者の勲功に対して上製の茶を贈与したものである。しかし、この時期における茶の飲み方はきわめて原始的なものであった。茶の葉を蒸して臼に入れてつき、団子として、米、薑、塩、橘皮、香料、牛乳等、時には葱とともに煮るのであった。この習慣は現今チベット人および蒙古種族の間に行なわれていて、彼らはこれらの混合物で一種の妙なシロップを造るのである。ロシア人がレモンの切れを用いるのは ――彼らはシナの隊商宿から茶を飲むことを覚えたのであるが―― この古代の茶の飲み方が残っていることを示している。
茶をその粗野な状態から脱して理想の域に達せしめるには、実に唐朝の時代精神を要した。八世紀の中葉に出た陸羽(三)をもって茶道の鼻祖とする。かれは、仏、道、儒教が互いに混淆せんとしている時代に生まれた。その時代の汎神論的象徴主義に促されて、人は特殊の物の中に万有の反映を見るようになった。詩人陸羽は、茶の湯に万有を支配しているものと同一の調和と秩序を認めた。彼はその有名な著作茶経(茶の聖典)において、茶道を組織立てたのである。爾来彼は、シナの茶をひさぐ者の保護神としてあがめられている。
茶経は三巻十章よりなる。彼は第一章において茶の源を論じ、第二章、製茶の器具を論じ、第三章、製茶法を論じている(四)。彼の説によれば、茶の葉の質の最良なものは必ず次のようなものである。
胡人の鞾のごとくなる者蹙縮然たり(五) 犎牛の臆なる者廉襜然たり(六) 浮雲の山をいずる者輸菌然たり(七) 軽飈の水を払う者涵澹然たり(八) また新治の地なる者暴雨流潦の経る所に遇うがごとし(九)
第四章はもっぱら茶器の二十四種を列挙してこれについての記述であって、風炉(一〇)に始まり、これらのすべての道具を入れる都籃に終わっている。ここにもわれわれは陸羽の道教象徴主義に対する偏好を認める。これに連関して、シナの製陶術に及ぼした茶の影響を観察してみることもまた興味あることである。シナ磁器は、周知のごとく、その源は硬玉のえも言われぬ色合いを表わそうとの試みに起こり、その結果唐代には、南部の青磁と北部の白磁を生じた。陸羽は青色を茶碗に理想的な色と考えた、青色は茶の緑色を増すが白色は茶を淡紅色にしてまずそうにするから。それは彼が団茶を用いたからであった。その後宋の茶人らが粉茶を用いるに至って、彼らは濃藍色および黒褐色の重い茶碗を好んだ。明人は淹茶を用い、軽い白磁を喜んだ。
第五章において陸羽は茶のたて方について述べている。彼は塩以外の混合物を取り除いている。彼はまた、これまで大いに論ぜられていた水の選択、煮沸の程度の問題についても詳述している。彼の説によると、その水、山水を用うるは上、江水は中、井水は下である。煮沸に三段ある。その沸、魚目(一一)のごとく、すこし声あるを一沸となし、縁辺の涌泉蓮珠(一二)のごとくなるを二沸となし、騰波鼓浪(一三)を三沸となしている。団茶はこれをあぶって嬰児の臂のごとく柔らかにし、紙袋を用いてこれをたくわう。初沸にはすなわち、水量に合わせてこれをととのうるに塩味をもってし、第二沸に茶を入れる。第三沸には少量の冷水を鍑に注ぎ、茶を静めてその「華(一四)」を育う。それからこれを茶碗に注いで飲むのである。これまさに神酒! 晴天爽朗なるに浮雲鱗然たるあるがごとし(一五)。その沫は緑銭の水渭に浮かべるがごとし(一六)。唐の詩人盧同の歌ったのはこのような立派な茶のことである。
一椀喉吻潤い、二椀孤悶を破る。三椀枯腸をさぐる。惟う文字五千巻有り。四椀軽汗を発す。平生不平の事ことごとく毛孔に向かって散ず。五椀肌骨清し。六椀仙霊に通ず。七椀吃し得ざるに也ただ覚ゆ両腋習々清風の生ずるを。蓬莱山はいずくにかある 玉川子この清風に乗じて帰りなんと欲す(一七)。
茶経の残りの章は、普通の喫茶法の俗悪なこと、有名な茶人の簡単な実録、有名な茶園、あらゆる変わった茶器、および茶道具のさし絵が書いてある。最後の章は不幸にも欠けている。
茶経が世に出て、当時かなりの評判になったに違いない。陸羽は代宗(七六三―七七九)の援くるところとなり、彼の名声はあがって多くの門弟が集まって来た。通人の中には、陸羽のたてた茶と、その弟子のたてた茶を飲み分けることができる者もいたということである。ある官人はこの名人のたてた茶の味がわからなかったために、その名を不朽に伝えている。
宋代には抹茶が流行するようになって茶の第二の流派を生じた。茶の葉は小さな臼で挽いて細粉とし、その調製品を湯に入れて割り竹製の精巧な小箒でまぜるのであった。この新しい方法が起こったために、陸羽が茶の葉の選択法はもちろん、茶のたて方にも多少の変化を起こすに至って、塩は永久にすてられた。宋人の茶に対する熱狂はとどまるところを知らなかった。食道楽の人は互いに競うて新しい変わった方法を発見しようとした、そしてその優劣を決するために定時の競技が行なわれた。徽宗皇帝(一一〇一―一一二四)はあまりに偉い芸術家であって行ないよろしきにかなった王とはいえないが、茶の珍種を得んためにその財宝を惜しげもなく費やした。王みずから茶の二十四種についての論を書いて、そのうち、「白茶」を最も珍しい良質のものであるといって重んじている。
宋人の茶に対する理想は唐人とは異なっていた、ちょうどその人生観が違っていたように。宋人は、先祖が象徴をもって表わそうとした事を写実的に表わそうと努めた。新儒教の心には、宇宙の法則はこの現象世界に映らなかったが、この現象世界がすなわち宇宙の法則そのものであった。永劫はこれただ瞬時 ――涅槃はつねに掌握のうち、不朽は永遠の変化に存すという道教の考えが彼らのあらゆる考え方にしみ込んでいた。興味あるところはその過程にあって行為ではなかった。真に肝要なるは完成することであって完成ではなかった。かくのごとくして人は直ちに天に直面するようになった。新しい意味は次第に生の術にはいって来た。茶は風流な遊びではなくなって、自性了解の一つの方法となって来た。王元之は茶を称揚して、直言のごとく霊をあふらせ、その爽快な苦味は善言の余馨を思わせると言った。蘇東坡は茶の清浄無垢な力について、真に有徳の君子のごとく汚すことができないと書いている。仏教徒の間では、道教の教義を多く交じえた南方の禅宗が苦心丹精の茶の儀式を組み立てた。僧らは菩提達磨の像の前に集まって、ただ一個の碗から聖餐のようにすこぶる儀式張って茶を飲むのであった。この禅の儀式こそはついに発達して十五世紀における日本の茶の湯となった。
不幸にして十三世紀蒙古種族の突如として起こるにあい、元朝の暴政によってシナはついに劫掠征服せられ、宋代文化の所産はことごとく破壊せらるるに至った。十七世紀の中葉に国家再興を企ててシナ本国から起こった明朝は内紛のために悩まされ、次いで十八世紀、シナはふたたび北狄満州人の支配するところとなった。風俗習慣は変じて昔日の面影もなくなった。粉茶は全く忘れられている。明の一訓詁学者は宋代典籍の一にあげてある茶筅の形状を思い起こすに苦しんでいる。現今の茶は葉を碗に入れて湯に浸して飲むのである。西洋の諸国が古い喫茶法を知らない理由は、ヨーロッパ人は明朝の末期に茶を知ったばかりであるという事実によって説明ができるのである。
後世のシナ人には、茶は美味な飲料ではあるが理想的なものではない。かの国の長い災禍は人生の意義に対する彼の強い興味を奪ってしまった。彼は現代的になった、すなわち老いて夢よりさめた。彼は詩人や古人の永遠の若さと元気を構成する幻影に対する崇高な信念を失ってしまった。彼は折衷家となって宇宙の因襲を静かに信じてこんなものだと悟っている。天をもてあそぶけれども、へりくだって天を征服しまたはこれを崇拝することはしない。彼の葉茶は花のごとき芳香を放ってしばしば驚嘆すべきものがあるが、唐宋時代の茶の湯のロマンスは彼の茶碗には見ることができない。
日本はシナ文化の先蹤を追うて来たのであるから、この茶の三時期をことごとく知っている。早くも七二九年聖武天皇奈良の御殿において百僧に茶を賜うと書物に見えている。茶の葉はたぶん遣唐使によって輸入せられ、当時流行のたて方でたてられたものであろう。八〇一年には僧最澄茶の種を携え帰って叡山にこれを植えた。その後年を経るにしたがって貴族僧侶の愛好飲料となったのはいうまでもなく、茶園もたくさんできたということである。宋の茶は一一九一年、南方の禅を研究するために渡っていた栄西禅師の帰国とともにわが国に伝わって来た。彼の持ち帰った新種は首尾よく三か所に植え付けられ、その一か所京都に近い宇治は、今なお世にもまれなる名茶産地の名をとどめている。南宋の禅は驚くべき迅速をもって伝播し、これとともに宋の茶の儀式および茶の理想も広まって行った。十五世紀のころには将軍足利義政の奨励するところとなり、茶の湯は全く確立して、独立した世俗のことになった。爾来茶道はわが国に全く動かすべからざるものとなっている。後世のシナの煎茶は、十七世紀中葉以後わが国に知られたばかりであるから、比較的最近に使用し始めたものである。日常の使用には煎茶が粉茶に取って代わるに至った、といっても粉茶は今なお茶の中の茶としてその地歩を占めてはいるが。
日本の茶の湯においてこそ始めて茶の理想の極点を見ることができるのである。一二八一年蒙古襲来に当たってわが国は首尾よくこれを撃退したために、シナ本国においては蛮族侵入のため不幸に断たれた宋の文化運動をわれわれは続行することができた。茶はわれわれにあっては飲む形式の理想化より以上のものとなった、今や茶は生の術に関する宗教である。茶は純粋と都雅を崇拝すること、すなわち主客協力して、このおりにこの浮世の姿から無上の幸福を作り出す神聖な儀式を行なう口実となった。茶室は寂寞たる人世の荒野における沃地であった。疲れた旅人はここに会して芸術鑑賞という共同の泉から渇をいやすことができた。茶の湯は、茶、花卉、絵画等を主題に仕組まれた即興劇であった。茶室の調子を破る一点の色もなく、物のリズムをそこなうそよとの音もなく、調和を乱す一指の動きもなく、四囲の統一を破る一言も発せず、すべての行動を単純に自然に行なう―― こういうのがすなわち茶の湯の目的であった。そしていかにも不思議なことには、それがしばしば成功したのであった。そのすべての背後には微妙な哲理が潜んでいた。茶道は道教の仮りの姿であった。
- 『インド生活の組織』 ―― The Sister Nivedita 著。
- Paul Kransel 著、Dissertations, Berlin, 1902.
- 陸羽 ―― 字は鴻漸、桑苧翁と号した。唐の徳宗時代の人。
- 茶経には一之源、二之具、三之造とある。
- 胡人の鞾のごとくなる者蹙縮然たり ―― 如二胡人鞾一者蹙縮然。鞾は高ぐつ。蹙縮は鞾の針縫いの所のしまり縮まるを言う。
- 犎牛の臆なる者廉襜然たり ―― 犎牛臆者廉襜然。犎牛は野牛。廉襜は衣装などの裁ち目たたみ目などのそろったさま。これは犎牛の臆のすじの通ったのを言う。
- 浮雲の山をいずる者輪菌然たり ―― 浮雲出レ山者輪菌然。輪菌は丸くてねじける。雲のたちのぼるさまを言う。
- 軽飈の水を払う者涵澹然たり ―― 軽飈払レ水者涵澹然。涵澹は水のさま。少し波立つ状態を言う。
- また新治の地なる者暴雨流潦の経る所に遇うがごとし ―― 又如三新治地着遇二暴雨流潦之所一レ経。新治の地は瓦礫を去ったやわらかな土面、雨水にあった跡を言う。潦は路上の流水。
- 風炉 ―― 灰うけ、風炉とは風を通すによって名づける。今の風炉は名のみのこるものである。
- 魚目 ―― 小さい湯玉を魚目にたとえる。
- 縁辺の涌泉蓮珠 ―― 湯のにえあがるのを泉にたとえ、湯玉の多いのを連珠にたとえる。
- 騰波鼓浪 ―― 波だち、波うつ。
- 「華」 ―― 茶気。
- 晴天爽朗なるに浮雲鱗然たるあるがごとし ―― 如三晴天爽朗有二浮雲鱗然一。雲のかたちを魚のうろこにたとえる。
- その沫は緑銭の水渭に浮かべるがごとし ―― 其沫者若三緑銭浮二於水渭一。緑銭とは水草の葉。渭は湄の字が正しいであろう。
- 一椀喉吻潤い、二椀孤悶を破る。三椀枯腸をさぐる。惟うに文字五千巻有り。四椀軽汗を発す。平生不平の事ことごとく毛孔に向かって散ず。五椀肌骨清し。六椀仙霊に通ず。七椀吃し得ざるに也ただ覚ゆ両腋習々清風の生ずるを。蓬莱山はいずくにかある玉川子この清風に乗じて帰りなんと欲す。 ―― 一椀喉吻潤。二椀破二孤悶一。三椀捜二枯腸一、惟有二文字五千巻一。四椀発二軽汗一。平生不平事尽向二毛孔一散。五椀肌骨清。六椀通二仙霊一。七椀吃不レ得、也唯覚両腋習習清風生。蓬莱山在二何処一、玉川子乗二此清風一欲二帰去一。枯腸は文藻の乏しきを言う。習習は春風の和らぎ舒びるかたち。玉川子とは盧同自身をさす。
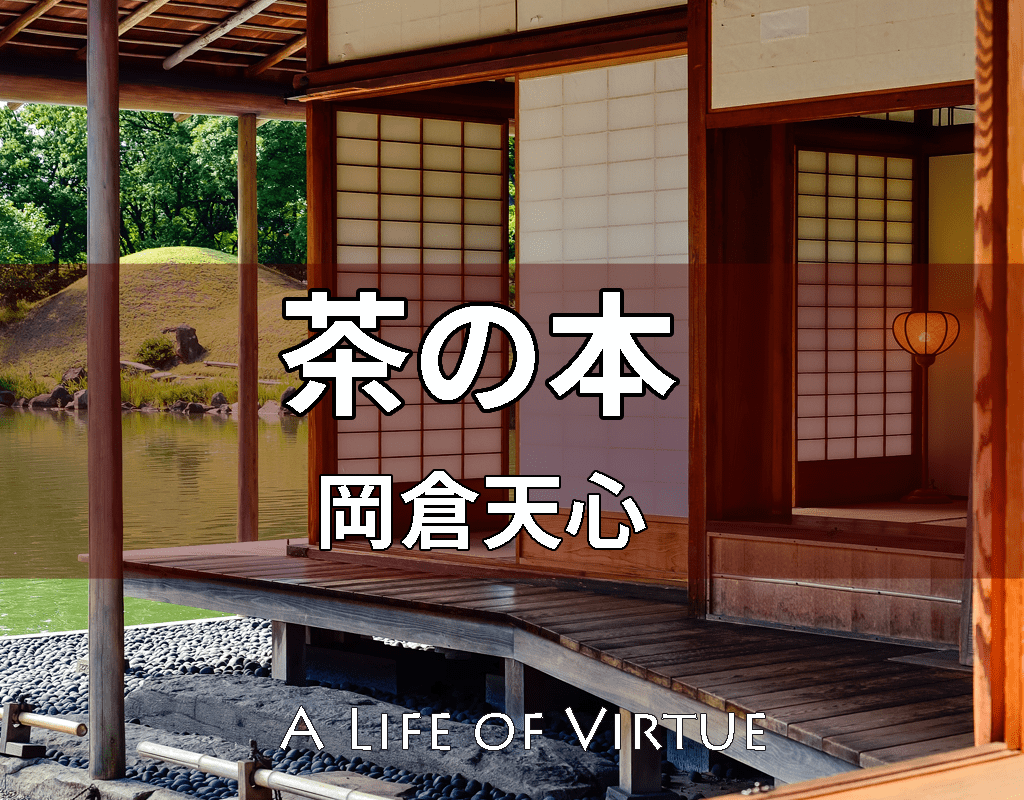 p.2
p.2