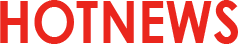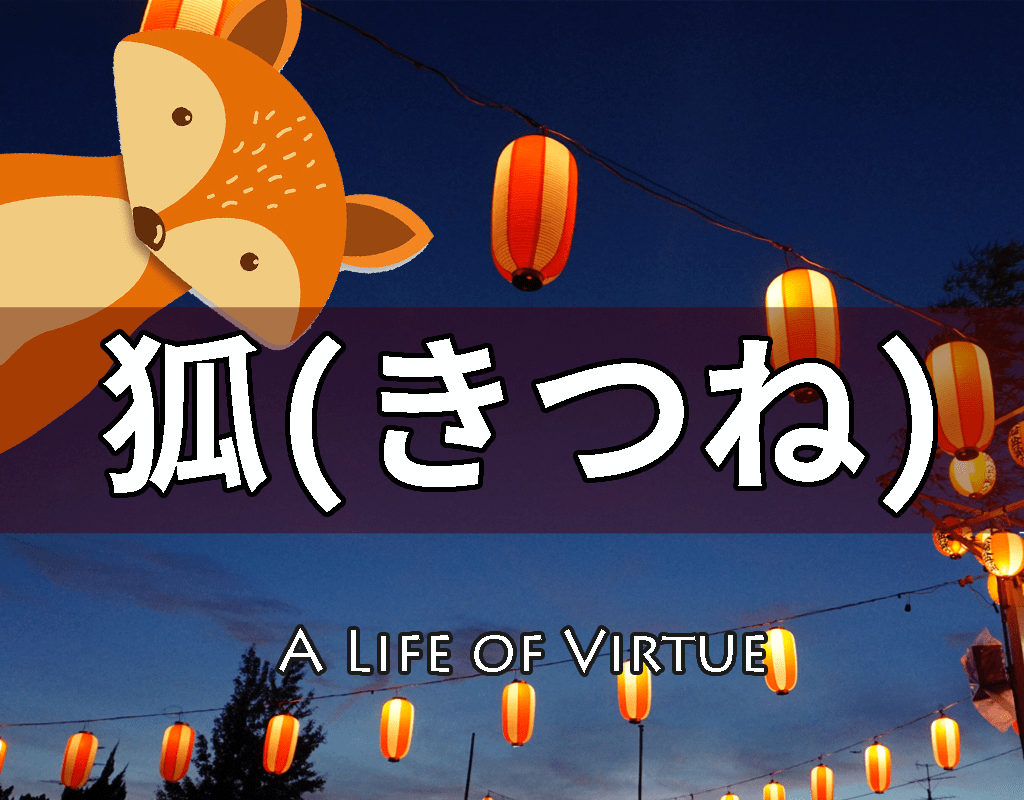 p.2
p.2
五
さてみんなは、とうとう、水車のところに来ました。水車の横から細い道がわかれて草の中を下へおりてゆきます。それが文六ちゃんの家にゆく道です。
ところが、今夜は誰も、文六ちゃんのことを忘れてしまったかのように、送ってゆこうとするものがありません。忘れたどころではありません、文六ちゃんがこわいのです。
甘えん坊の文六ちゃんは、それでも、いつも親切な義則君だけは、こちらへ来てくれるだろうと思って、うしろをむきむき、水車のかげになってゆきました。
とうとう、だれも文六ちゃんといっしょにゆきませんでした。
さて文六ちゃんは、ひとりで、月にあかるい谷地へおりてゆく細道をくだりはじめました。どこかで、
文六ちゃんは、ここから、じぶんの家までは、もうじきだから、誰も送ってくれなくても、困るわけではないのです。だが、いつもは送ってくれたのです、今夜にかぎっておくってくれないのです。
文六ちゃんは、ぼけんとしているようでも、もうちゃんと知っているのです、みんなが、じぶんの下駄のことで何といいかわしたか、また、じぶんが
祭にゆくまでは、あんなに、じぶんに親切にしてくれたみんなが、じぶんが、夜新しい下駄をはいて狐にとりつかれたかしれないために、もう誰一人かえりみてくれない、それが文六ちゃんにはなさけないのでした。
義則君なんか文六ちゃんより四年級も上だけれど親切な子で、いつもなら、文六ちゃんが寒そうにしていると、洋服の上に着ている
文六ちゃんの屋敷の外囲いになっている
――ひょっとすると、じぶんはほんとうに狐につかれているかもしれない、ということでした。そうすると、お父さんやお母さんはじぶんをどうするだろうということでした。
六
お父さんが樽屋さんの組合へいつて、今晩はまだ帰らないので、文六ちゃんとお母さんはさきに
文六ちゃんは初等科三年生なのにまだお母さんといっしょに寝るのです。ひとり子ですからしかたないのです。
「さあ、お祭の話を、母ちゃんにきかしておくれ」
とお母さんは、文六ちゃんのねまきのえりを合わせてやりながらいいました。
文六ちゃんは、学校から帰れば学校のことを、町にゆけば町のことを、映画を見てくれば映画のことをお母さんにきかれるのです。文六ちゃんは話が
「
と文六ちゃんは話しました。
お母さんは、そうかい、といって、面白そうに笑って、
「それから、もう誰が出たかわからなかったかい」
とききました。
文六ちゃんはおもいだそうとするように、眼を大きく見ひらいて、じっとしていましたが、やがて、祭の話はやめて、こんなことをいいだしました。
「母ちゃん、夜、新しい下駄おろすと、狐につかれる?」
お母さんは、文六ちゃんが何をいい出したかと思って、しばらく、あっけにとられて文六ちゃんの顔を見ていましたが、今晩、文六ちゃんの身の上に、おおよそどんなことが起ったか、けんとうがつきました。
「誰がそんなことをいった?」
文六ちゃんはむきになって、じぶんのさきの問いをくりかえしました。
「ほんと?」
「
「嘘だね?」
「嘘だとも」
「きっとだね」
「きっと」
しばらく文六ちゃんは黙っていました。黙っている間に、大きい眼玉が二度ぐるりぐるりとまわりました。それからいいました。
「もし、ほんとだったらどうする?」
「どうするって、何を?」
とお母さんがききかえしました。
「もし、僕が、ほんとに狐になっちゃったらどうする?」
お母さんは、しんからおかしいように笑いだしました。
「ね、ね、ね」
と文六ちゃんは、ちょっとてれくさいような顔をして、お母さんの胸を両手でぐんぐん押しました。
「そうさね」と、お母さんはちょっと考えていてからいいました。「そしたら、もう、家におくわけにゃいかないね」
文六ちゃんは、それをきくと、さびしい顔つきをしました。
「そしたら、どこへゆく?」
「
「母ちゃんや父ちゃんはどうする?」
するとお母さんは、
「父ちゃんと母ちゃんは相談をしてね、かあいい文六が、狐になってしまったから、わしたちもこの世に何のたのしみもなくなってしまったで、人間をやめて、狐になることにきめますよ」
「父ちゃんも母ちゃんも狐になる?」
「そう、二人で、
文六ちゃんは大きい眼をかがやかせて、
「鴉根って、西の方?」
「
「深い山?」
「松の木が
「猟師はいない?」
「猟師って鉄砲打ちのことかい? 山の中だからいるかも知れんね」
「猟師が撃ちに来たら、母ちゃんどうしよう?」
「深い
「でも、雪が降ると
「そしたら、いっしょうけんめい走って逃げましょう」
「でも、父ちゃんや母ちゃんは速いでいいけど、僕は子供の狐だもん、おくれてしまうもん」
「父ちゃんと母ちゃんが両方から手をひっぱってあげるよ」
「そんなことをしてるうちに、犬がすぐうしろに来たら?」
お母さんはちょっと黙っていました。それから、ゆっくりいいました。もうしんからまじめな声でした。
「そしたら、母ちゃんは、びっこをひいてゆっくりいきましょう」
「どうして?」
「犬は母ちゃんに
文六ちゃんはびっくりしてお母さんの顔をまじまじと見ました。
「いやだよ、母ちゃん、そんなこと。そいじゃ、母ちゃんがなしになってしまうじゃないか」
「でも、そうするよりしようがないよ、母ちゃんはびっこをひきひきゆっくりゆくよ」
「いやだったら、母ちゃん。母ちゃんがなくなるじゃないか」
「でもそうするよりしようがないよ、母ちゃんは、びっこをひきひき ゆっくりゆっくり……」
「いやだったら、いやだったら、いやだったら!」
文六ちゃんはわめきたてながら、お母さんの胸にしがみつきました。涙がどっと流れて来ました。
お母さんも、ねまきのそででこっそり眼のふちをふきました、そして文六ちゃんがはねとばした、小さい
「狐(きつね)」というタイトルからは想像もつかない、感動のラストシーン。
自己犠牲の愛は気高く美しい。まさに「母親の愛は 海より深い」ですね。