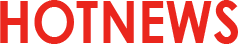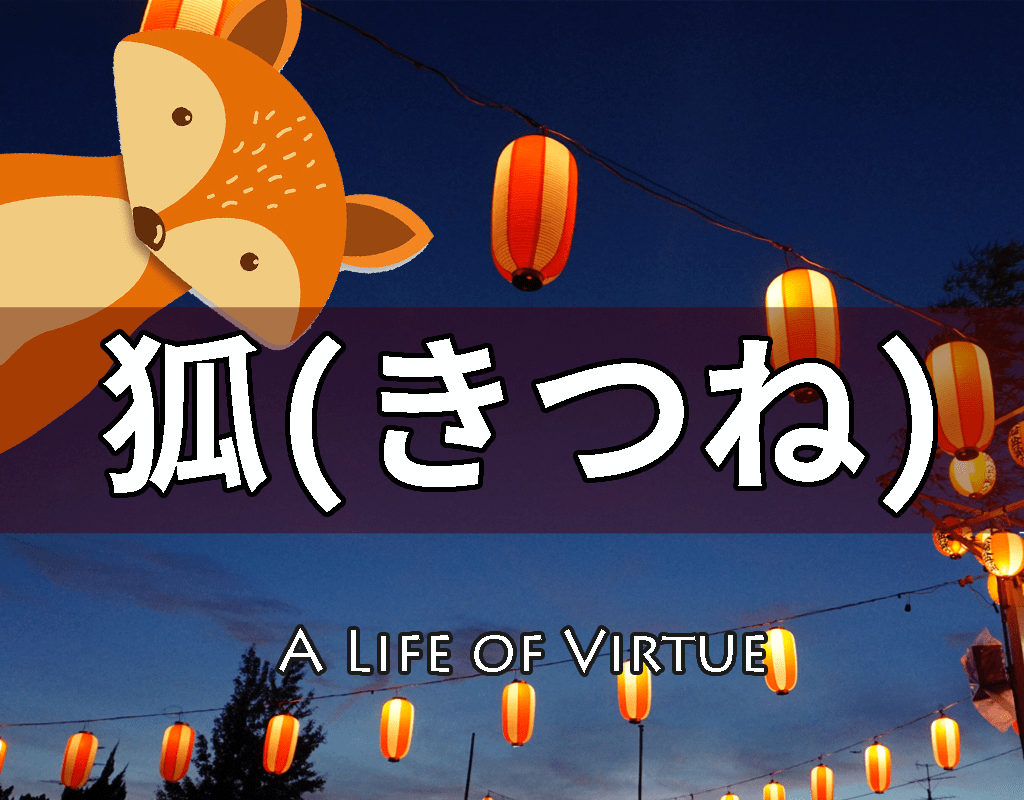新美南吉 著『狐(きつね)』
【ひとこと紹介】友達は全員裏切っても 母ちゃんだけは絶対に自分を見捨てない…。涙せずにはいられない感動のラスト。母親の愛は、海より深くて偉大なり。
一
月夜に七人の子供が歩いておりました。
大きい子供も小さい子供もまじっておりました。
月は、上から照らしておりました。子供たちの影は短かく
子供たちはじぶんじぶんの影を見て、ずいぶん大頭で、足が短いなあと思いました。
そこで、おかしくなって、笑い出す子もありました。あまりかっこうがよくないので二、三歩はしって見る子もありました。
こんな月夜には、子供たちは何か夢みたいなことを考えがちでありました。
子供たちは小さい村から、半里ばかりはなれた
切通しをのぼると、かそかな春の夜風にのって、ひゅうひゃらりゃりゃと笛の
子供たちの足はしぜんにはやくなりました。
すると一人の子供がおくれてしまいました。
「
とほかの子供が呼びました。
文六ちゃんは月の光でも、やせっぽちで、色の白い、眼玉の大きいことのわかる子供です。できるだけいそいでみんなに追いつこうとしました。
「んでも
と、とうとう鼻をならしました。
なるほど細長いあしのさきには大きな、
二
本郷にはいるとまもなく、道ばたに下駄屋さんがあります。
子供たちはその店にはいってゆきました。文六ちゃんの下駄を買うのです。文六ちゃんのお母さんに頼まれたのです。
「あののイ、
と、
「こいつのイ、
みんなは、樽屋の清さの子供がよく見えるように、まえへ押しだしました。それは文六ちゃんでした。文六ちゃんは二つばかり
小母さんは笑い出して、下駄を
どの下駄が足によくあうかは、足にあてて見なければわかりません。義則君が、お父さんか何ぞのように、文六ちゃんの足に下駄をあてがってくれました。何しろ文六ちゃんは、一人きりの子供で、甘えん坊でした。
ちょうど文六ちゃんが、新しい下駄をはいたときに、腰のまがったお
「やれやれ、どこの子だか知らんが、晩げに新しい下駄をおろすと
子供たちはびっくりしてお婆さんの顔を見ました。
「
とやがて義則君がいいました。
「迷信だ」
とほかの一人がいいました。
それでも子供たちの顔には何か心配な色がただよっていました。
「ようし、そいじゃ、小母さんがまじないしてやろう」
と、下駄屋の小母さんが口軽くいいました。
小母さんは、マッチを一本するまねして、文六ちゃんの新しい下駄のうらに、ちょっと
「さあ、これでよし。これでもう、狐も
そこで子供たちは下駄屋さんを出ました。
三
子供たちは
「あれ、トネ子だよ、ふふ」
とささやきあったりしました。
稚児さんを見てるのに飽くと、くらいところにいって、
舞台を照らすあかるい電燈には、虫がいっぱい来て、そのまわりをめぐっていました。見ると、舞台の正面のひさしのすぐ下に、大きな、あか土色の
子供たちは山車の鼻の下にならんで、仰向いて、人形の顔を見ていました。
人形は
するととつぜん、パクッと人形が口をあきペロッと舌を出し、あっというまに、もとのように口をとじてしまいました。まっかな口の中でした。
これも、うしろで糸をひく人がやったことです。子供たちはよく知っているのです。ひるまなら、子供たちは面白がって、ゲラゲラ笑うのです。
けれど子供たちは、いまは笑いませんでした。
―― 子供たちは思い出しました、文六ちゃんの新しい下駄のことを。晩げに新しい下駄をおろすものは狐につかれるといったあの婆さんのことを。
子供たちは、じぶんたちが、ながく遊びすぎたことにも気がつきました。じぶんたちにはこれから帰ってゆかねばならない、半里の、野中の道があったことにも気がつきました。
四
かえりも月夜でありました。
しかし、かえりの月夜は、なんとなくつまらないものです。子供たちは、だまって ――ちょうど一人一人が、じぶんのこころの中をのぞいてでもいるように、だまって歩いていました。
切通し坂の上に来たとき、一人の子が、もう一人の子の耳に口を寄せて何かささやきました。するとささやかれた子は別の子のそばにいって何かささやきました。その子はまた別の子にささやきました。 ――こうして、文六ちゃんのほか、子供たちは何か一つのことを、耳から耳へいいつたえました。
それはこういうことだったのです。「下駄屋さんの
それから子供たちはまたひっそりして歩いてゆきました。ひっそりしているとき子供たちは考えておりました。
――狐につかれるというのはどんなことかしらん。文六ちゃんの中に狐がはいることだろうか。文六ちゃんの姿や形はそのままでいて、心は狐になってしまうことだろうか。そうすると、いまもう、文六ちゃんは狐につかれているかもしれないわけだ。文六ちゃんは黙っているからわからないが、心の中はもう狐になってしまっているかもしれないわけだ。
おなじ月夜で、おなじ野中の道では、誰でもおなじようなことを考えるものです。そこでみんなの足はしぜんにはやくなりました。
ぐるりを低い桃の木でとりまかれた池のそばへ、道が来たときでした。子供たちの中で誰かが、
「コン」
と小さい
ひっそりして歩いているときなので、みんなは、その小さい音でさえ、聞きおとすわけにはゆきませんでした。
そこで子供たちは、今の咳は誰がしたか、こっそり調べました。すると――文六ちゃんがしたということがわかりました。
文六ちゃんがコンと咳をした! それなら、この咳にはとくべつの意味があるのではないかと子供たちは考えました。よく考えて見るとそれは咳ではなかったようでした。狐の鳴声のようでした。
「コン」
とまた文六ちゃんがいいました。
文六ちゃんは狐になってしまったと子供たちは思いました。わたしたちの中には狐が一匹はいっていると、みんなは恐ろしく思いました。