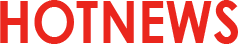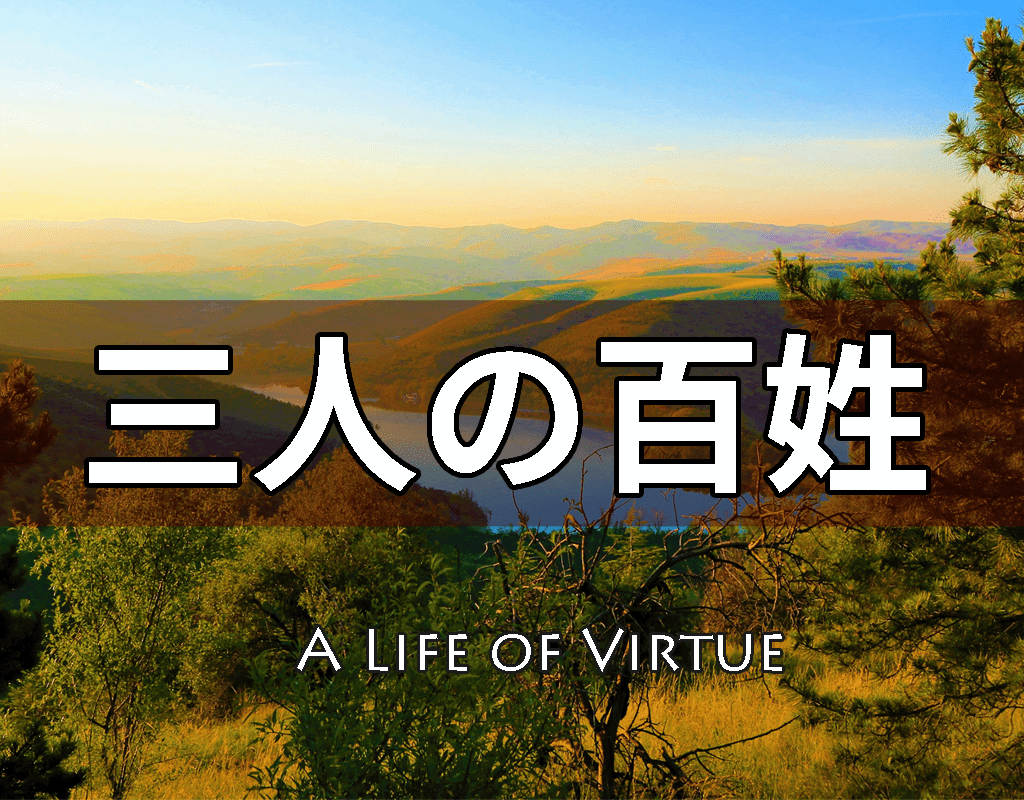秋田雨雀 著『三人の百姓』
【ひとこと紹介】「子供がいると毎日が楽しい」「大金よりも子供がいるほうが幸せ」 そんな "当たり前" に気づかせてくれるお話。
三人の百姓
昔、ある北の国の山奥に一つの村がありました。その村に
三人の百姓の生れた村というのは、それはそれは
伊作、多助、太郎右衛門の三人は、ある秋の末に、いつものように背中に炭俵を三俵ずつ背負って城下へ出かけて行きました。三人が村を出た時は、まだ河の流れに朝霧がかかって、
「今日も、はあお天気になるべいてや。」
と伊作が橋を渡りながら、
「そんだ、お天気になるてや。」
と調子を合わせて、橋を渡って行きました。
三人はいつものように、炭を売ってしまった
伊作は
峠を越すと、広い平原になって、そこから城下の方まで、十里四方の水田がひろがって、田には
「伊作の足あ、なんて早いんだべい!」
と多助は太郎右衛門に言いました。
「ああした男あ、坂の下で一服やってる頃だべい。」
と太郎右衛門は笑いながら答えました。
多助と太郎右衛門が、峠を越して平原の見えるところまで来た時、坂の下の方で伊作が一生懸命に二人の方を見て、手を振っているのが、見えました。
「どうしたんだべいな? 伊作あ、
と多助が言いました。太郎右衛門も顔をしかめて坂の下を見下しました。
「早く来い、早く来い……面白いものが
という伊作の声がきこえて来ました。
「面白いものが
と多助は、笑いながら言うと、太郎右衛門も大きな口を
「伊作の拾うんだもの、
と太郎右衛門は附け足して、多助と一緒に少し急いで坂を下りて行きました。
坂の下の方では、伊作はさも、もどかしそうに、二人の下りて来るのを待っていました。
「
と多助は、炭俵をがさがささせて、走って行きました。
太郎右衛門は、根がはしっこくない男でしたから、多助に遅れて、一人で坂を下りて行きました。太郎右衛門が伊作のいたところへ着いた時には、伊作と多助は大事そうにして、何か持ち上げて見たり
「何あ、
と太郎右衛門は
「見ろ、こうしたものあ、落ってるんだてば。」
と伊作は、少し
「ははあ! これあ、奇体な話でねいか!」
と太郎右衛門は叫びました。今三人の前に生れてから三月ばかり
「一体
多助は赤児の顔を見て、
「それさ、いい着物を着て、ただ者の子供じゃあんめいよ。そんだとも、うっかり手をつけられねいぞ。かかり合いになって
と
「そうだども、
と、気の弱い太郎右衛門は言いました。
「子供も不憫には不憫だども、
と
すると、赤児の腹のところに、三角にくけた
「
伊作の発議でとにかく三人はその赤児を拾うことにきめました。
「この金はとにかく、
と伊作はさっさと自分の腹へ巻きつけようとしましたので、それを見た多助は、大変に
「お前に子供がないわで、この子供を育てたらよかべい。」
と言いました。
太郎右衛門は、その時伊作に向って、
「
と言ってどうしても金を受取りませんでした。
多助は、もし太郎右衛門が受取らなければその五枚も伊作に取られてしまうのを知っているので、是非受取るようにすすめたけれども受取りませんでした。伊作は太郎右衛門がどうしても受取らないので、その内の二枚を多助にくれて、
三人は城下へ行くのをやめて、その日は自分の村へ帰ってしまいました。